営業職がきつい理由とは? 具体的な対処法やメンタルの管理方法、スキルアップについて解説

営業として働く中で、「きつい」と感じた経験がある人は多いかもしれません。実際、数ある職種の中でも、営業職はきついと言われがちなポジションと言えます。この記事では、営業職がきついと言われる理由や具体的な対処法を解説します。
9Eキャリアの転職支援サービス
9Eキャリアは、営業職の中でも将来性の高い職種に特化して転職支援を行っています。
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
営業職がきついと感じる理由
営業職がきついと感じる人は、具体的にどのようなポイントに悩みを抱えているのでしょうか。よくある8つの理由を紹介します。
ノルマ達成を求められる
営業がきついと感じる大きな理由として、ノルマ達成を求められる点が関係しています。業界の違いにかかわらず、多くの企業は営業に対して一定期間内に達成すべき目標を設定しています。売上や受注数、新規顧客の獲得数などの数値が決められており、ノルマ達成を徹底しなくてはいけません。ノルマ未達になった際の上司からの叱責を想像して、強いストレスを感じる人もいるでしょう。中でも、月末や年度末が近づいてもノルマ未達の場合、短期間で成果を上げなくてはいけないプレッシャーがかかります。
契約が取れない場合のストレスが大きい
営業成績は数字として表れるため、上司だけでなく同僚にも把握されやすい点が特徴です。営業として努力を重ねても、契約を取れなければ社内評価が下がりかねません。上司の叱責に加えて周囲からも白い目で見られることで、職場での居心地が悪くなってしまうでしょう。また、同僚の成果を把握できることから、好成績を収めているメンバーと自分を比較して落ち込んでしまう場合もあります。努力を重ねてもなかなか成果につながらない状況では、さらにストレスは大きくなります。
残業が多くなりやすい
営業職は、他の職種と比べると残業が多くなりやすい傾向にあります。ノルマを達成するためには、テレアポや顧客訪問、プレゼン資料の作成、商談といった数多くの業務が発生します。顧客への訪問時間は先方の都合に合わせる必要があり、自分の裁量で業務時間を調整することは難しいでしょう。外回り営業を終えた後にデスクワークを行うパターンも多く、結果的に残業が増えやすいです。残業時間が増えるほど体力を消耗してしまうため、しっかりと休めずにストレスが溜まります。
営業成績に追われる
営業職は、基本的に成績に追われ続けます。月間のノルマを達成できても、また来月のノルマがあるためです。さらに、営業職の給与体系は、基本給にインセンティブを加えた形式を採用している企業が珍しくありません。営業成績が給与に直結することから、安定した成果を出さなくてはいけないプレッシャーがかかります。しかし、毎月優れた営業成績を維持できる自信がない場合、「給与が減ってしまうかもしれない」と不安を抱くでしょう。とりわけ、基本給が低い会社であれば不安は強くなります。
業務量が給与に直結するわけではない
契約を取るために努力したり業務量を増やしたりしても、必ずしも給与に直結するわけではありません。企業の評価制度にもよりますが、結果的に契約を取れなければ評価へなかなかつながらないでしょう。どれほど顧客を分析して対策を練っても、相手が商品・サービスを望まない状態であれば成約には至りません。しかし、営業経験を積むことでスキルアップにつながるため、成約できずとも意義はあります。一方で、数字でわかる成果を得られないことで、「徒労に終わった」とモチベーションが下がってしまう人もいるでしょう。
営業先にあしらわれる・断られる
営業先の対応によって、きついと感じるケースもあるでしょう。営業先の担当者は、すべての人が丁寧に対応してくれるとはかぎりません。単に営業を断られるだけでなく、冷たくあしらわれたり怒鳴られたりなど、厳しい態度をとられる場合もあります。また、一定の信頼関係がある既存顧客へのルート営業に比べると、新規開拓営業のほうがストレスは溜まりやすいと言えます。まったく関係性を築けていない相手に営業するため、冷たく対応されてしまう機会は多いでしょう。
高いコミュニケーション能力が必要になる
営業職は顧客と密接にやり取りするため、高いコミュニケーション能力が必要です。コミュニケーションスキルに不安がある場合、きついと感じやすくなります。課題のヒアリングや商材・サービスのプレゼンなど、顧客から信頼を得なくてはいけない場面は多岐にわたります。初対面の人であっても、相手の業界や人となりに合わせて臨機応変に対応しなくてはいけません。顧客へ自らアプローチして懐に入り込む必要があるため、コミュニケーションが苦手な人にはつらい仕事となります。
商品・サービスに自信がない
営業がきついと感じる理由に、売り込むべき自社の商品・サービスに自信がないパターンも挙げられます。たとえ他社に優れた製品があると考えていても、営業は自社の商材を顧客へ勧めなくてはいけない立場です。本当はおすすめしたくないと思っている商材を売り込む場合、罪悪感を感じてしまうかもしれません。自社の商品・サービスの強みを理解しないままだと、後ろめたい気持ちを抱えながら顧客へ営業することにストレスを感じるでしょう。
営業手法ごとのきついと言われるポイント
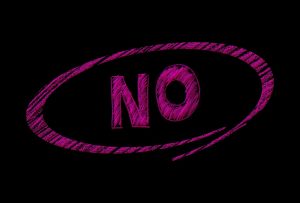
同じ営業の仕事でも、手法によってきついと言われる細かなポイントは異なります。代表的な営業手法ごとに、負担がかかりがちなポイントを見ていきましょう。
飛び込み営業
新規開拓のために行う飛び込み営業は、これまで取引のない相手にアポイントなしで訪問する営業手法です。個人宅を1件ずつ回ったり、オフィスビルを1棟または1階ごとに訪問したりすることから、体力も求められます。しかし、事前に面会の約束を取っていないため、門前払いになるケースがほとんどです。成功率の低さを前提にした方法であるため、いくら断られてもめげない精神力がなければハードな仕事となるでしょう。成功体験を積み上げるまでに時間がかかりやすい点も、きついと感じる理由になり得ます。
テレアポ営業
テレアポ営業とは、電話で見込み客へアプローチする営業手法です。直接訪問する手間はかかりませんが、その分だけ1日何件もの電話をかける必要があります。電話越しでは表情が見えないため、音声のみで相手の興味の度合いを推測しなければいけません。さらに、「営業電話」とわかった瞬間に電話を切られたり、怒鳴られたりする場合もあります。1日に何度も架電しなくてはいけないうえ、厳しい対応を受けることもあるために「きつい」と感じる人が存在します。
代理店営業
代理店営業とは、販売代理店に自社の商材を拡販してもらうための営業活動を指します。代理店は複数の会社と取引しており、自社の商材を優先して売り込んでもらえるような提案が不可欠です。単に商品の魅力を伝えるだけではなく、担当者との信頼関係を築いて販売の動機付けを行う必要があります。加えて、代理店営業は顧客と直接関わりを持たず、思ったように商材が売れなくともすぐに改善策を実行できません。提案した改善策を代理店が実行してくれないがゆえに、ストレスを感じる場合があります。
個人営業
個人営業とは、法人ではなく個人を顧客とするBtoCビジネスの営業形態です。法人営業と比較して顧客との距離感が近く、1人ひとりの生活や価値観に寄り添ったアプローチが求められます。しかし、寄り添ったアプローチを行う以前に、そもそも営業というだけで拒否感を持たれることもあるでしょう。個人の顧客は自分で裁量できるため、ろくに話を聞いてもらえず門前払いを受けるケースも少なくありません。また、土日や祝日などの顧客の休日に合わせて稼働する機会もあることから、不規則な働き方がきついと感じるかもしれません。
ルート営業
ルート営業とは、既存顧客へ定期的に訪問して商材の追加購入やアップグレードを提案する営業手法です。飛び込み営業やテレアポと比べれば、すでに関係性のある取引先が相手であることから精神的な負担は少ない傾向にあります。しかし、ルート営業では、顧客との長期的な関係継続のために臨機応変な対応が常に求められます。小さな不満を放置すれば他社に乗り換えられる可能性があるゆえに、綿密なヒアリングが必要です。緊急のトラブル対応や綿密なサポートなど、安定している分だけ地道なフォローが必須となるでしょう。
営業がきついと言われがちな業界

営業のきつさは、業界によっても違いがあります。市場の競争状況や商材の性質によって、次の4つの業界は「営業がきつい」とされています。
保険・金融業界
保険や金融業界は、競争が激しいことから営業がきつくなりがちです。生命保険や損害保険、投資商品など、顧客が選べる金融商品は無数に存在します。顧客に自社の商品を契約してもらうためには、他社との差別化を明確に打ち出したうえで信頼を勝ち取らなければなりません。また、保険業界の営業は基本給+歩合制の給与体系が一般的です。契約を取るべきプレッシャーが強い点も、営業がきついと言われる理由となっています。
広告業界
広告業界の営業は、広告を出稿するクライアントと制作会社の仲介役となります。クライアントの要望を正確にくみ取って制作側に伝えるだけでなく、制作側のスケジュール等の事情をクライアントに理解してもらう必要もあります。とはいえ、基本的にはクライアントの要望を優先的に叶えなくてはいけないため、制作側に無理なお願いをせざるを得ない場合もあるでしょう。双方の間に立つことから板挟みになりやすく、精神的に疲弊する人もいます。
不動産業界
不動産業界の営業は、住宅や土地などの高額な商品を扱う点が特徴です。成約までのハードルが高く、顧客1人ひとりから信頼を獲得するために入念なフォローを行わなくてはいけません。さらに、不動産の営業手法は再現性が低いとも言えます。住宅や土地の購入は人生に関わる買い物であることから、顧客の意思決定には感情も含めた複雑な要因が絡みます。理屈だけでなく顧客の背景や感情に寄り添ったアプローチも必要なため、個々のスキルが大きく問われるでしょう。
IT業界
近年、需要が拡大しているIT業界もまた、営業がきついとされています。IT業界の営業色は、基本の営業スキルに加えて自社サービスに関する専門知識も必要です。また、自社サービスの仕様を正しく理解するために、前提となる技術的な知識も求められます。加えて、顧客の要望を反映したサービスを提案する場合、実現可能な仕様でなくてはいけません。開発面の知識がなければ、実現困難な機能や見積り、スケジュールを提案してしまうリスクがあります。顧客と開発側の調整役になることから、負担を感じる人もいるでしょう。
営業がきつくないと言われる業界

営業職は「きつい」「つらい」といったイメージを持たれがちですが、すべての業界で厳しいわけではありません。営業が比較的きつくないと言われる業界を4つ紹介します。
インフラ業界
インフラ業界は、電気やガス、水道、通信、交通機関といった生活に欠かせないサービスを提供する分野です。インフラサービスは社会基盤と密接していることから、需要が安定しています。インフラ会社の営業対象は法人や公的機関が中心となり、既存顧客との取引継続や代理店のサポートが中心となります。新規開拓の営業活動が少ないため、顧客に断られ続けてストレスを感じる機会は多くありません。
食品業界
食品業界も、営業がきつくないとされる業界の1つです。食品は消費者の生活に直結するために景気の影響を受けづらく、常に一定の需要が見込めます。食品メーカー同士の競争が存在する一方で、新規参入は少ない点も特徴です。工場の新設や厳しい衛生管理が必要になることから参入障壁は高く、競争が激化しづらいです。食品メーカーの営業先は既存顧客がメインとなるため、営業職には新商品や売り場拡大、キャンペーンなどの提案が主に求められます。
化学業界
化学業界とは、化学反応によって合成繊維や合成ゴムといった化学素材や、洗剤や化粧品などの最終製品を製造する分野です。化学製品の製造には、高度な技術や大規模な設備投資が不可欠です。簡単に新規参入できるわけではないため、市場全体が安定傾向にあります。中でも、素材作りを行う化学メーカーは、自社の素材を最終製品の製造メーカーへ卸す立場です。取引先は既存顧客が中心となるため、厳しい新規開拓の営業の必要性は低いと言えます。
医薬品業界
医薬品業界は化学業界と構造が似ており、営業があまりきつくない分野です。医薬品の開発には莫大な研究開発費が必要になり、薬機法による規制も存在します。たとえば、医薬品の製造・販売には「医薬品製造販売業許可」の取得が必須です。取得市場に存在する企業は限られているため、営業担当者が無理に新規ターゲットへ売り込む必要がありません。また、医薬品の開発サイクルは長く、製品が短期間で他の製品に置き換わるケースは少ないです。病院や薬局などの既存顧客と長期間の関係を構築できるため、営業の負担も軽くなります。
営業職がきついと感じやすい人の特徴

営業職は成果が評価へ直結するため、やりがいのある仕事です。その反面、性格によっては強いストレスを感じやすい仕事とも言えます。営業職がきついと感じやすい人の特徴を5つ解説します。
コミュニケーションに不安がある
営業職は多くの人と関わるため、コミュニケーションに不安がある場合はきついと感じやすいでしょう。人と話すこと自体に苦手意識があったり、初対面の相手に緊張しすぎてしまったりすると、顧客とスムーズに会話できません。どのような人が顧客であっても、営業職は相手のニーズや不満を聞き出す必要があります。そのうえで自社商材の魅力をアプローチして、購買の意思決定を引き出す話術も重要です。人との関わりに負担を感じる場合、営業で大きなストレスを抱えてしまうかもしれません。
完璧主義の傾向がある
営業は、必ずしもすべての活動が成果に直結するとはかぎりません。どれほど顧客に寄り添って丁寧に接触を続けても、相手の事情やタイミングによって断られるケースはよくあります。営業は断られることが前提ですが、完璧主義の人は受け入れにくいかもしれません。1つの失敗を大きく考えて過剰に落ち込み、営業活動そのものが苦しくなるおそれがあります。営業は、場数を踏むことで成果につながる仕事です。しかし、完璧主義の人にとっては、その過程こそが「きつい」と悩む可能性があります。
他人の反応を気にしすぎる
営業では顧客の反応を見てトークを変える技量が求められますが、相手の反応を気にしすぎると逆効果になるおそれがあります。話す内容が二転三転すると、一貫性のない説明に終始してしまうでしょう。顧客から信用を得られないうえに、必要以上に譲歩した提案をしてしまうリスクも生じます。相手の要望を優先しすぎれば、仮に成約しても大した利益を得られません。そのため、他人の反応を常に意識してしまう人は営業成績を上げづらく、精神的な負担を感じやすいといえるでしょう。
自己管理を苦手としている
自己管理が苦手な場合、営業がつらくなる可能性があります。営業職はただ顧客と話すだけではなく、資料作成やリード選定、アポイント調整、見積り作成、既存顧客のフォローアップ、メンバー・他部署との連携といった多岐にわたる業務を並行して進める必要があります。作業の優先順位づけやタスク管理を適切に行わなければ、重要な仕事が後回しになってしまうでしょう。セルフマネジメントを怠ると業務のスピード感に振り回され、「いつも仕事に追われている」と切迫感を感じる原因となります。
営業用の柔和な対応ができない
営業においては、顧客に合わせた柔らかい対応が大切です。事実のみを淡々と話しても、堅苦しく冷たい印象を与えてしまうだけです。「購入後のサポートが手薄そう」「トラブル時に対応してくれなさそう」と顧客に警戒心を抱かせてしまえば、商談は上手くいきません。したがって、営業職には相手の警戒心を解く人当たりの良さが求められます。相手に寄り添った対応や笑顔が苦手な場合、なかなか成果につながらず「きつい」と悩む可能性が高まります。
営業職がきついと悩んでいるときの対処法

営業がきついと感じた際に、そのまま放置してしまうとモチベーションの低下を招きます。成績の低迷を招き、悪循環に陥ってしまうおそれがあります。営業がきついと悩んでいる場合、以下6つの対処法に取り組んでみてください。
上司や同僚に悩みを相談する
現在悩んでいる点について、まずは上司や同僚に相談しましょう。自分1人で抱え込んでしまうと、悩みがどんどん大きくなって冷静な判断ができなくなります。上司や同僚に相談することで、現状に対して客観的なアドバイスをもらえます。業界にもよりますが、営業トークはある程度の再現性があるものです。成功経験にもとづいた改善案をもらえれば、自身の営業トークについて見直すべき方向性がわかるでしょう。また、単に悩みを聞いてもらうだけでも、ストレス解消の一環になります。
ノルマ達成に向けて適切なKPIを設定する
ノルマ達成に向けた道筋としてKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。営業をきついと感じる理由に、ノルマの存在は大きく関わります。厳しいと感じるノルマであっても、
小さな目標を設定すればモチベーションを維持しやすくなります。ノルマ達成に必要な要素を分解して、1日や1週間あたりの「アポイント獲得数」「訪問件数」「新規リード獲得数」などの数値を決めましょう。ノルマに向かって漠然と行動するのではなく、小さな目標を少しずつクリアしていくことで達成感を積み重ねていけます。
業務に優先順位をつける
営業の仕事は幅広いため、業務を細分化して優先順位をつけましょう。やるべき作業が山積みになると、本来優先すべき仕事を放置してしまうリスクがあります。顧客への対応が遅れれば、受注機会を逃してしまうかもしれません。まずは作業を洗い出して、「緊急度」と「重要度」で以下の順番で分類しましょう。
1.重要度と緊急度ともに高い
2.重要度は高いが、緊急度は低い
3.重要度は低いが、緊急度は高い
4.重要度と緊急度ともに低い
優先すべき業務を特定できるため、生産性の向上が可能です。常にタイムマネジメントを意識することで、限られた時間で最大限のパフォーマンスを発揮できるでしょう。また、無駄な残業の削減にもつながります。
ツールを活用する
営業活動が忙しすぎる場合、きついと感じる一因となります。そこで、必要に応じてツールを活用すれば、業務量を減らせるでしょう。たとえば、SFA(営業支援ツール)であれば、案件の進捗管理や見込み客の状況を一目で把握できます。さらに、CRM(顧客関係管理)は顧客ごとの対応履歴や要望を整理できるため、提案の質を高められます。こうした各種ツールを導入することで、事務作業に費やす時間の大幅な削減が可能です。営業職のコア業務である、顧客へのアプローチや商談、クロージングに集中できるでしょう。
失注分析を行う
商談を進めても最終的に受注できなかった「失注」に対して何もせず流してしまうと、同じ失敗を繰り返す可能性が高いです。失注分析を行えば、営業プロセスのどこがボトルネックとなっているのかを明らかにできます。「価格が原因で他社に乗り換えられた」「課題の解決策として商材の強みを伝えきれていなかった」など、失注の理由を分析することで具体的な改善策を考えられます。営業職を安定して続けるためには、次回こそ成約につなげるための分析と改善が大切です。
豊富な知識を身につける
自社の商品・サービスの情報だけでなく、ターゲット層の業界についても豊富な知識を習得しましょう。商材への深い知識があれば顧客からの質問に的確に答えられるため、自然と説得力が増します。さらに、顧客の業界の動向や特徴を把握している場合、顧客が直面している課題を深く理解できます。顧客の課題に対して適切な商材をおすすめできるうえ、具体的な活用方法を提案できるでしょう。根拠とともに自社の商品やサービスを推奨できることから、顧客からの信頼を獲得しやすくなります。
営業職がきつい際はスキルアップも重要

営業職は明確な成果を求められる仕事ですが、精神的な負担を和らげるためにはスキルアップが重要です。営業スキルが向上すれば成果を上げやすくなり、業務への自信も高まります。ここでは、営業職のスキルアップ方法を5つ紹介します。
成果にかかわらず営業活動を振り返る
成約や失注などの成果の違いにかかわらず、営業活動を振り返りましょう。成功と失敗のパターンの分析を繰り返せば、さらに伸ばすべきポイントや改善すべき点がわかります。成約につながった商談の場合、顧客が興味を示したポイントや意思決定の後押しになったトークを整理しましょう。一方、商談につながらなかった架電や失注した商談であれば、どこで顧客に一歩引かれてしまったのかを分析してみてください。成功と失敗の両面から振り返ることで、再現性の高い営業スタイルを確立できます。
成果を上げている人を参考にする
営業職の中で優れた成果を出している人を参考にすると、スキルアップへつながります。ひと口に営業活動と言っても、商談の組み立て方法や顧客との距離の縮め方、クロージングのタイミングといったポイントは人によって異なります。参考にしたい人に同行したり、録音や録画を見たりして、優秀な人のノウハウを吸収しましょう。また、直接アドバイスを求めることで、自分では気づかない課題を把握でき、効率的な改善が可能です。成功している人の思考プロセスや工夫を学べば、独学ではわからないナレッジを得られるでしょう。
セミナーや研修に参加する
社内だけでなく、外部のセミナーや研修に参加する方法もおすすめです。営業スキルに関するセミナーでは、提案力の強化や商談のテクニック、クロージングのコツ、最新の営業トレンドなどの幅広い内容を学べます。社外の専門家や他業種の営業担当者との交流によって、新しい視点を得られる点も大きなメリットです。加えて、セミナーでは同じように悩んでいる営業職の人々とも交流できます。同じように悩んでいる仲間がいると実感できることから、気持ちの面でも前向きになれるでしょう。
顧客の課題解決を意識する
営業スキルを向上させるためには、顧客の課題解決を意識した提案力の習得も大切です。契約を取りたいばかりに商品を一方的に売り込んでも、顧客には響きません。顧客は製品そのものを欲しているのではなく、課題を解決できる商品やサービスを求めています。顧客が抱えている課題について仮説を立て、自社の商品・サービスの効果的な活用方法をまとめましょう。単なる機能や性能の説明だけでなく、顧客の悩みに寄り添った具体的な解決法を示すことで強く訴求できます。
トレーニングを重ねる
実践的な営業スキルは、先輩への同行や座学だけでは身につきません。本番を想定したトレーニングを重ねることで、実際の架電や商談で活かせるスキルを習得できます。よくあるトレーニング方法が、上司や先輩が顧客役になる「ロープレ(ロールプレイング)」です。ロープレを行う際は、初回面談やテストクロージングなどのシーンを設定して進めます。ロープレの実施後は、上司や先輩からその場ですぐにフィードバックをもらえます。声のトーンや話すスピード、説明の順序といった細かなポイントを修正していけば、本番で顧客へ与える印象を大きく改善できるでしょう。
営業職がきついと感じるときのメンタル管理方法

営業は成果が数字で明確に示されるため、ストレスを抱えやすい仕事です。メンタルが不安定になれば仕事に集中できなくなり、余計に成果が遠のくかもしれません。営業職がきついと感じている場合、次の4つのメンタル管理方法を試してみてください。
「営業は断られるもの」と理解する
過剰に落ち込まないためのマインドとして、「営業は断られるもの」と考えましょう。中でも、新規開拓の飛び込み営業やテレアポは、断られるケースのほうが圧倒的に多いです。そもそも営業の成功には、相手が新たな商材を求めるタイミングの良さも関わります。もちろんリード育成も重要ですが、運の要素を完全には排除できません。また、営業活動は提案やターゲット選定の質だけでなく、より多くの人に接触することも求められます。質を高めながら数を重ねていけば、いずれ成功へとつなげられるでしょう。
成功体験を記録する
上手くいかなかった営業ばかりにとらわれず、成功体験にもきちんと目を向けましょう。ネガティブな経験のほうが記憶に残りがちですが、意識的にポジティブな体験にも注目することでメンタルを安定させられます。具体的には、アポイントを取れた電話の会話内容や、成約につながったプレゼンを記録しておきましょう。加えて、顧客からの良い反応も細かく残して、いつでも読めるようにしてみてください。営業がつらく気持ちが落ち込んだときに読み返せば、自信を取り戻すきっかけとなるでしょう。
休日と仕事を切り離す
メンタルを健康的に保つためには、休日と仕事は完全に切り離しましょう。営業は顧客対応やデスクワークなどのやるべき作業が多く、休日でも仕事が頭から離れない人も多いのではないでしょうか。ですが、常に仕事を意識していると心が休まる時間がなく、精神的な疲労が積み重なってしまいます。また、休日に睡眠や食事をおろそかにして、トークスクリプトの作成や会話の練習を行うと体力を回復できません。しっかり休むことで心身ともに疲れがリセットされるため、翌週の仕事にも集中しやすくなります。
好きなことでリフレッシュする
終業後や休日には、好きなことでリフレッシュしてストレスを解消しましょう。好きなことは人それぞれですが、運動や趣味への集中がおすすめです。たとえば、筋トレやランニングなどの運動で体を動かすと、ストレスを発散できるうえに達成感も得られます。読書や映画・音楽鑑賞といった趣味に没頭すれば、心を落ち着かせられるでしょう。加えて、家族や友人と過ごす時間も大切です。悩みや愚痴を聞いてもらうことで、「また明日から頑張ろう」と気持ちを切り替えられるでしょう。
営業職がきつい場合はやりがいを見つけよう

営業職はきついと言われがちですが、楽しさや充実感を見いだして活躍している人もいます。営業をきついと感じている場合、やりがいを見つけることでストレスを和らげられるでしょう。ここでは、営業職ならではの主なやりがいを4つ説明します。
成果を数字で確認できる
営業の成果は、商談獲得数や成約数、売上高といった形で、数字としてわかりやすく表れます。そのため、自分の成長や努力の成果をはっきり確認できる点が特徴です。営業は利益を直接生み出すポジションであることから、自分の努力が確実に企業の成長に直結していると実感できます。また、数字で成果を示される点は、社内評価や給与にも影響します。インセンティブ制を導入している企業では、成果に応じて給与が上がる仕組みです。報酬面でも成果が反映されるため、営業職として大きなやりがいを感じられるでしょう。
成長を実感しやすい
営業の成果が数字で表れる点は、自分の成長を実感しやすいとも言い換えられます。セミナーへの参加やロープレの積み重ねによって、商談獲得数や成約数が増えれば大きな喜びを得られるでしょう。また、数字上の成果だけでなく、顧客とのやりとりを通しても成長を感じられます。「自社の製品をプレゼンした際の反応がよくなった」「会話の中で自然とクロージングに入れるようになった」など、小さな変化が努力の結実を物語ってくれます。営業職は人と向き合う仕事だからこそ、相手の反応によって達成感を得られるわけです。
人脈を広げられる
営業職は多くの人と直接コミュニケーションを取るため、幅広い人と信頼関係を築いて人脈を広げられます。人脈はリファラル営業による新規顧客の創出に加えて、自身の長期的なキャリアを支える財産にもなります。さらに、多様なネットワークによって、業界の最新動向や顧客のニーズ変化をいち早く得られる点もメリットです。こうした情報が新しい提案や商談のきっかけとなることで、さらなる成果へと結びつきます。仕事を通じた人とのつながりが新たな利益を生む仕組みは、営業職ならではのやりがいとなります。
顧客から感謝や信頼を寄せられる
営業職のやりがいとして、顧客から直接感謝や信頼を寄せられる点も挙げられます。営業職は単純に製品やサービスを売るだけでなく、顧客をサポートする役割もあります。商品やサービスを通じて顧客の課題を解決していけば、少しずつ信頼を獲得できるでしょう。顧客への貢献を言葉で伝えられる喜びは、モチベーションを高めてくれます。営業活動では要望やクレームを受けるときもありますが、その分だけ感謝や信頼を得られた際の喜びは格別となります。
営業職の転職を考える際のポイント

営業職はやりがいや達成感がある一方で、「きつい」と感じ続ける場合は転職したほうがいい可能性もあります。しかし、勢いだけで転職を決断してしまうと、後悔する事態になりかねません。営業職の転職を考える際は、以下3つのポイントを意識しましょう。
本当に転職するべきなのかを検証する
はじめに、本当に転職したほうがいいのかを考えましょう。営業の仕事がきついと感じる理由は、ノルマのプレッシャーや人間関係、商材への不安、働き方といったさまざまな原因があります。たとえば、人間関係に悩みがある場合、部署移動や社内の環境改善により解決できるかもしれません。まずは上司に相談して、解決を試みてみましょう。一方で、商材を好きになれなかったり、働き方に不満があったりする場合、前向きに転職を検討したほうがいいと言えます。
転職先の職種を考える
転職する場合、営業職を続けるのか、もしくは他の職種を目指すのかを決めましょう。営業職を続けたい場合、業界や営業スタイルを変えることで負担が軽くなるケースがあります。例として、テレアポ中心の新規開拓型から既存顧客との関係構築がメインのルート営業に転職すれば、ストレスの質は大きく変わります。そもそも営業の適性に不安がある場合、営業経験を活かせる他の職種への挑戦を検討しましょう。具体的には、カスタマーサクセスやキャリアアドバイザーなどの職種は、営業からの転職先として一定の人気があります。
転職エージェントを利用する
転職の方向性を決めた後は、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは非公開求人を多く保有しており、利用者1人ひとりに寄り添ったサポートを提供しています。中でも、営業専門の転職エージェントであれば、利用者の営業経験を評価したうえで適切な求人を紹介してもらえます。たとえば、「9Eキャリア」は営業特化型の転職支援を行う転職エージェントです。書類作成や面接対策に加えて、中長期のキャリア形成を前提とした幅広いサポートを提供しています。
営業がきついときはスキルアップやメンタル管理が大切
ノルマ達成や数字による評価によって、営業職をきついと感じる人は少なくありません。営業手法によって悩むポイントは異なりますが、中でも飛び込み営業やテレアポはきついと感じやすいでしょう。営業で悩んでいる際は、上司への相談や失注分析などの方法で対処してみてください。また、スキルアップによって営業成果を改善することでも、つらさを解消できます。どうしても営業のきつさを解決できない場合、転職も検討しましょう。
9Eキャリアで後悔のない営業職転職を
9Eキャリアは、営業職への転職に特化した転職エージェントです。営業未経験者にも対応しており、キャリアの棚卸しから書類添削、面接対策、検索では見つからない非公開求人の紹介まで一貫して無料で支援しています。
また、営業職への転職に特化した”求職者のことを1番に考える”伴走型転職エージェントです。
①“特化型”だからできる、他では出会えない厳選求人
②企業の裏側まで熟知したエージェントによる支援
③書類も面接も通過率が上がる、伴走型の転職支援
という特徴があります。
9Eキャリアの転職支援サービス
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
この記事の監修者
荒川 翔貴
学生時代に100名規模の営業団体を設立後、大手メーカーで新人賞、売上4,000%増を達成。その後人材業界に転身し、ベンチャー企業にて求職者・企業双方を支援。プレイヤーとして社内売上ギネスを塗り替えながら、3年で事業部長に昇進し組織マネジメントも経験する。
現在は株式会社9Eのキャリアアドバイザーチームリーダーとして、入社半年で再び社内ギネスを更新するなど、常に成果を追求し続けている。(▶︎詳しく見る)
