営業戦略・戦術に欠かせないフレームワーク23選!活用手順から注意点まで解説

営業戦略を立てろと言われても、そもそも何から手をつければいいのか分からない。
現場ではこうした声が絶えません。実際、営業企画やマネージャーが3C分析やSWOTなどのフレームワークを使ってみたものの、単なる穴埋め作業で終わってしまい、実際の戦術やKPIに接続できていないケースも少なくありません。
特にBtoB営業の現場では、意思決定プロセスが複雑で、属人的な手法だけでは成果の再現性が担保できません。だからこそ重要なのが、「正しいフレームワークを、正しい順番で、目的に応じて使い分ける」ことです。
本記事では、営業戦略・戦術の立案から実行・改善までを一貫して支えるフレームワーク23種類を体系的に解説します。さらに、よくある失敗例や選び方のコツ、現場への落とし込み方まで、実務で使える視点に落とし込んで紹介していきます。
9Eキャリアの転職支援サービス
9Eキャリアは、営業職の中でも将来性の高い職種に特化して転職支援を行っています。
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
そもそもフレームワークとは
営業戦略や戦術を構築する際に役立つのがフレームワークです。フレームワークとは、複雑な事象を特定の視点で整理・分析する思考の型を指します。
営業現場では、何を基準に意思決定すべきか分からなくなったり、属人的な判断に頼ったりする場面が少なくありません。そこでフレームワークを使えば、思考の順序や分析のポイントが明確になり、感覚に頼らず、論理的に戦略や施策を立案できます。
また、単なる分析ツールではなく、チーム間での共通言語や業務標準化の手段としての役割も大きく、再現性のある営業活動を実現する基盤となります。
営業戦略と営業戦術の違い

営業戦略とは、会社や事業部が中長期的に目指すべき方向性を明確にする方針や目標を指します。新規市場の開拓、LTV(顧客生涯価値)の最大化、シェア拡大などが対象です。
一方で営業戦術は、その戦略を実現するための短期的な行動計画を意味します。特定業種向けのセミナー開催やターゲット企業向け提案資料の作成などが含まれます。
両者は混同されがちですが、戦略がなければ戦術は空回りし、戦術がなければ戦略は実現性を欠いた計画にとどまります。明確な戦略に基づいて戦術を展開し、両者を有機的に連携させることが、成果を最大化する鍵となります。
営業戦略・戦術でフレームワークを活用するメリット

営業にフレームワークを取り入れると、属人性の排除、再現性の確保、戦略と戦術の整合性の維持といった多くのメリットが得られます。各メリットの詳細を見ていきましょう。
属人化の排除とナレッジ共有の促進
営業の現場では、経験豊富な担当者のノウハウが暗黙知として蓄積されがちです。
フレームワークを活用すれば、個人の勘や経験に依存せず、誰でも同じプロセス・方法で行動できます。結果として、ベテランと新人のギャップが縮まり、組織全体の営業力が底上げされるわけです。
さらに、トークスクリプトや提案資料に落とし込むことで、ナレッジの形式知化も促されます。
再現性のあるPDCAサイクルが回せる
施策を実行した後に成功・失敗の理由を言語化するのは難しいものですが、フレームワークを使えば仮説検証の基盤が明確になります。
たとえば、3C分析を基に仮説を立てて施策に反映し、その結果を同じ視点で検証すれば、属人的な感想ではなく論理的な検証が可能です。これによりPDCAサイクルが回りやすくなり、改善の精度も高まります。
戦略と戦術の整合性を担保できる
戦略と戦術が乖離してしまう要因のひとつに、両者をつなぐ共通言語の不足があります。
フレームワークは、戦略段階で設定したターゲットや差別化要素を、戦術に落とし込む橋渡しの役割を果たします。たとえば、STP分析で「中堅製造業の購買部門」をターゲットと定めたなら、戦術ではその層に響く導入事例や信頼性訴求を展開すべきです。
逆に戦術が戦略とズレている場合でも、フレームワークに立ち返って見直すことが可能です。
営業戦略の立案で役に立つ主なフレームワーク15選

ここでは、営業戦略の立案で役立つ基本フレームワークを15選解説します。
3C分析【外部環境と自社の強みを整理】
3C分析とは、Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3視点で事業環境を整理するフレームワークです。顧客ニーズや競合他社の動き、自社の立ち位置を一体的に俯瞰し、機会とリスクのバランスを判断するのに役立ちます。
PEST分析【マクロ環境の変化を捉える】
PEST分析とは、Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の観点から外部環境をマクロ的に整理するフレームワークです。新法施行や業界再編といった大局的な変化が営業戦略に与える影響を可視化できます。
ファイブフォース分析【業界構造を理解する】
ファイブフォース分析とは、新規参入の脅威、業界内競合、代替品、買い手・売り手の交渉力という5要素から業界構造の分析を行うフレームワークです。競争の激しさや価格決定力を理解し、参入判断や差別化戦略の検討に活用できます。
SWOT分析【内外要因を統合的に評価】
SWOT分析とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4象限で内部・外部要因を確認するフレームワークです。どの市場で勝てるか、どんなリスクに備えるべきかを明確にできます。
VRIO分析【自社の強みの持続性を評価】
VRIO分析とは、Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織体制)の4要素で自社の強みを評価する手法です。営業人材やナレッジが本当に持続的な競争優位になっているかを判断できます。
バリューチェーン分析【価値創出の源泉を分解】
バリューチェーン分析とは、調達・製造・物流・営業・アフターサポートなどの活動を分解し、どの工程が価値を生んでいるかを整理するフレームワークです。営業活動では、商談で訴求すべき強みを見極めるのに有効です。
STP分析【ターゲット市場の選定と戦略の軸決定】
STP分析とは、Segmentation(市場細分化)、Targeting(標的市場選定)、Positioning(差別化戦略)の順で市場を整理するフレームワークです。営業のリソース配分やアカウント戦略を設計する際に欠かせません。
4P分析(マーケティングミックス)【営業戦術の骨格を設計】
4P分析とは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4観点から施策を設計するフレームワークです。製品の打ち出し方や価格戦略を明文化し、営業戦術に落とし込むのに役立ちます。
ビジネスモデルキャンバス【顧客価値と収益構造の整理】
ビジネスモデルキャンバスとは、9つの構成要素から事業全体を1枚で可視化するフレームワークです。顧客価値、チャネル、収益構造を整理し、商談設計や戦略立案の基盤として活用できます。
バリュープロポジションキャンバス【課題と価値の接続を設計】
バリュープロポジションキャンバスとは、顧客の課題や期待成果と、自社が提供できる価値を対応づけて設計するフレームワークです。課題解決型営業や提案営業における価値訴求を強化できます。
アンゾフの成長マトリクス【事業拡張の方向を明確化】
アンゾフの成長マトリクスとは、「市場×製品」の2軸から、市場浸透、新市場開拓、新製品開発、多角化の4つの方向を定義するフレームワークです。営業部門の成長戦略を描く際の基盤となります。
BCGマトリクス【営業リソースの最適配分】
BCGマトリクスとは、市場成長率と市場シェアの2軸から事業を「花形」「問題児」「金のなる木」「負け犬」に分類するフレームワークです。営業活動の重点配分や撤退判断に活用できます。
ランチェスター戦略【局所集中で勝ち筋を作る】
ランチェスター戦略とは、兵力やシェアの差を前提に「弱者の戦略」を設計するフレームワークです。リソースが限られた営業チームが、特定業種や地域でシェア拡大を狙う際に有効です。
パレートの法則(80:20)【重点顧客の選定】
パレートの法則とは、売上の8割は2割の顧客によって生み出されるという経験則です。最も収益性の高い顧客層に時間や人員などのリソースを集中し、効率的な成長を目指す指針として用いられます。
営業プロセスマッピング【営業活動の可視化と標準化】
営業プロセスマッピングとは、リード獲得から受注までの各ステージを行動・KPI・成果物に分解し、一元的に整理するフレームワークです。営業の標準化、OJT、マネジメント基盤として活用できます。
営業戦術で役に立つフレームワーク8選

ここでは、営業戦術を立てるのに役立つフレームワークを説明します。
BANT【案件の確度を定量的に判定】
BANTとは、Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(ニーズ)、Timeframe(導入時期)の4要素で案件の優先度を評価するフレームワークです。商談初期に活用することで、リードの温度感を見極め、営業活動の優先順位をつける基準となります。
MEDDIC【複雑商談での意思決定構造の可視化】
MEDDICとは、Metrics(評価指標)、Economic buyer(決裁者)、Decision criteria(意思決定基準)、Decision process(意思決定プロセス)、Identify pain(課題特定)、Champion(社内推進者)の6要素で案件を管理するフレームワークです。
多層的な意思決定が絡むBtoB大型商談に特に有効です。
SPIN話法【質問による課題深掘りとニーズ顕在化】
SPIN話法とは、Situation(状況)、Problem(問題)、Implication(示唆)、Need-payoff(解決価値)の順に質問を展開する対話型フレームワークです。顧客自身も気づいていない課題を引き出し、納得感のある提案につなげられます。
FABE分析【商品の魅力を論理的に訴求】
FABE分析とは、Feature(特徴)、Advantage(利点)、Benefit(顧客にとっての利益)、Evidence(根拠・実績)の4段階で提案を構成するフレームワークです。営業資料や提案トークを整理し、説得力を高めるのに有効です。
AIDMAモデル【オフライン営業における購買心理の設計】
AIDMAモデルとは、Attention(注目)→Interest(関心)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動)の流れで購入心理を捉えるフレームワークです。訪問営業やチラシ配布など、オフライン接点で効果的に活用できます。
AISASモデル【デジタル接点での行動設計】
AISASモデルとは、Attention(注目)→Interest(関心)→Search(検索)→Action(行動)→Share(共有)の流れで購買行動を整理するフレームワークです。Web広告やホワイトペーパーのダウンロードなど、オンライン施策設計に役立ちます。
クロージングトライアングル【成約条件の3軸を設計】
クロージングトライアングルとは、「感情的共感」「論理的納得」「人間関係の信頼」という3軸を満たすことで顧客の意思決定を促すフレームワークです。商談終盤での提案や態度に取り入れることで、成約率を高められます。
セールスステージ設計【営業行動のKPI可視化】
セールスステージ設計とは、商談をフェーズごとに分解し、それぞれにKPIと必要アクションを設定するフレームワークです。例として「架電数 → アポ率 → 提案実施率 → 受注率」と可視化することで、課題を数値で把握し改善に活かせます。
フレームワークを活用して営業戦略・戦術を立案するステップ
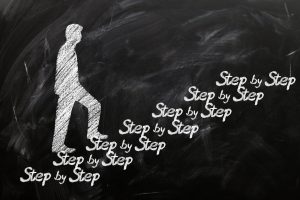
営業戦略・戦術の立案においては、フレームワークをただ使うだけでは意味がありません。適切な順序で活用することで、戦略の筋道が通り、戦術への落とし込みがスムーズになります。
ここでは、フレームワークを営業活動に活用する手順を解説するので、ぜひ参考にしてください。
STEP1:市場と外部環境を分析する
戦略設計のスタート地点は、「そもそも自分たちはどんな市場にいるのか?」という外部環境の把握です。
PEST分析を使えば、法制度の変化や業界再編、消費者行動の変容、テクノロジーの進展といったマクロ環境の潮流が読み取れます。
ファイブフォース分析では、競合の激しさやサプライヤーとの力関係、参入障壁などを評価し、業界内での戦い方の構造の把握が可能。
3C分析を通じて、市場全体(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3軸で全体像を整理し、最初の戦略仮説を立てましょう。
ここでは、「何が機会で、何が脅威なのか」を言語化できることが成果物です。
STEP2:自社の強みと経営資源を洗い出す
外部が見えたら、次は自社内部の現状を徹底的に棚卸しします。
SWOT分析を用いて、組織やサービスの「強みと弱み」を把握し、VRIO分析でその強みが持続可能で、模倣困難で、利益を生む資源かどうかを評価します。
たとえば、「営業人材の質が高い」と評価するだけでは不十分で、それが競合と比較してどれだけ優位性があり、仕組み化できるかまで分析する必要があります。
また、バリューチェーン分析を使えば、どの工程(インサイドセールス/技術営業/納品体制など)に価値が集中しているかを見極め、差別化戦略の源泉を構造的に可視化できます。
このフェーズでは、「自社が勝てる条件は何か?」を定義していきます。
STEP3:ターゲット顧客と戦う市場を定義する
戦略を広げる前に、あえて「捨てる」対象を決めることが重要です。
STP分析を用いて市場を細分化し、「誰に届けるか」を明確にします。ターゲットの抽象化ではなく、業種・職種・規模・課題レベルまで具体的に絞ることが成果につながります。
パレートの法則を適用すれば、売上の8割を生む2割の顧客層が誰なのかが見えてきます。さらに、ランチェスター戦略を使うことで、どのセグメントに集中すれば高確率で勝てるかという重点領域の設計が可能になるでしょう。
このステップの目的は、営業リソースの最適配分=選択と集中の設計です。
STEP4:営業戦略の方向性を設計する
ここからが戦略設計の中核フェーズです。
アンゾフの成長マトリクスを用いて、「既存市場×既存商品」か「新市場×新商品」かといった拡張軸の選択を行い、営業の方向性を定めましょう。
そのうえで、バリュープロポジションキャンバスを使い、顧客課題と提供価値の接続を設計。さらにビジネスモデルキャンバスを活用して、提供価値を収益につなげるビジネス構造の全体設計を行います。
戦略がこのフェーズで定まれば、以下の戦術や施策は一本の軸に沿って展開できるようになります。
STEP5:営業戦術を設計する
戦略を行動レベルに落とし込むフェーズです。
BANTやMEDDICを活用して顧客の案件化条件や意思決定構造を整理し、SPIN話法でニーズを深掘りします。そのうえで、FABE分析で提案の論理を組み立て、AIDMAやAISASで心理的・行動的導線を最適化していきます。
ここでのポイントは、営業メンバーによる再現性です。属人性に頼らず、どの顧客に対しても一定水準の提案ができるよう、スクリプトやテンプレートに落とし込みます。
STEP6:営業プロセスとKPIを可視化する
戦術を実行可能な仕組みに変換する段階です。
セールスステージ設計によって、営業フェーズごとに必要なアクション(アプローチ→ヒアリング→提案→クロージング)と行動KPI(架電数・アポ率・受注率など)を明文化します。
あわせて、カスタマージャーニーマップを活用すれば、顧客視点での感情・情報ニーズ・接点を可視化でき、営業のタイミングやコンテンツ設計も戦略的に整います。
成果が出ない原因を構造的に検証できる基盤がこのステップです。
STEP7:仕組みに落とし込み、PDCAを回す
設計した戦略・戦術を一時的な施策で終わらせないためには、継続的に回す仕組み化が不可欠です。
たとえば、「FABE構造で成功した提案」「失注したSPINの課題」などをチェックリストや事例テンプレートとして形式知化し、定期的にレビューする振り返りの仕組みを整備します。
このようなPDCAの土台があることで、属人的な成功体験が組織の営業資産として蓄積されていきます。戦略を作って終わりではなく、進化し続ける設計こそが営業部門の競争力になります。
営業戦略・戦術にフレームワークを使うポイント

フレームワークは、単に分析するためのテンプレートではありません。営業組織に定着させ、成果に結びつけるには使い方そのものに工夫が必要です。
まずは戦略から設計する
営業活動にフレームワークを導入する際、最も重要なのは使う順序です。
戦術やプロセス設計から入ってしまうと、部分最適にとどまり、全体としての成果が見えづらくなります。まず最初に着手すべきは、市場や外部環境の分析、そしてその結果をもとにした戦略の設計です。
たとえば、PESTや3C、STP分析を用いて外部環境とターゲット市場を明確化し、VRIO分析やバリューチェーン分析で自社の強みや資源を可視化することで、営業活動の勝ち筋が見えてきます。
その上で、SPIN話法やFABE分析といった関連する戦術系フレームワークを導入すれば、戦略の意図が現場の動きと整合する形で伝わるようになるでしょう。
戦略なき戦術は、単なる施策の乱発です。逆に、戦略に裏打ちされた戦術は、意思決定と行動が一貫した営業組織の礎となります。
属人化しない仕組みにする
フレームワークの導入でありがちな失敗は、「一部の優秀な営業担当だけが使いこなせている」状態にとどまってしまうことです。
これでは属人化を解消するどころか、逆に知識格差が広がるリスクすらあります。大切なのは、誰でも自然に使えるように業務フローに組み込むことです。
具体的には、SPIN話法の流れを営業トークスクリプトに組み込み、FABEの各要素を提案資料テンプレートに反映させる。BANTの4要素をCRM入力項目に変換し、案件登録のたびに自然と判断できるようにする。
こうした設計が、仕組みとしての再現性を生み出します。
さらに、会議の中でも「この提案のFABEで言うB(Benefit)は何か?」といった問いかけを共通言語にすることで、チーム全体がフレームワークを自分の言葉として使えるようになります。
フレームワークは組み合わせで戦術化する
単独のフレームワークでは、営業の複雑な実務課題に十分対応できないケースも多くあります。そこで有効なのが、複数のフレームワークを段階的に組み合わせて活用するというアプローチです。
一例をあげると、SPIN話法で顧客の課題や背景を深くヒアリングし、その情報をもとにFABE分析で製品・サービスの価値訴求を構成。そしてクロージングの場面では、クロージングトライアングルを用いて「感情・論理・信頼」の3軸すべてで納得感を得られるよう設計するといった具合です。
さらに、営業フェーズの上流においても、STP分析で選定したセグメントに対し、VRIO分析で導き出した自社の強みを当てはめ、アンゾフの成長マトリクスで成長方向を選定するといった戦略×戦術の複合設計も可能です。
このように、フレームワークを点ではなく線や面で活用することで、より高度で差別化された営業設計が実現できます。
どのフレームワークを使うべき?営業戦略・戦術のフレームワークの選び方

営業で使えるフレームワークは多岐にわたり、初心者でなくとも「何を使えばいいのか分からない」と悩むケースは少なくありません。
フレームワーク選定の第一歩は、目的別または営業フェーズ別に分類して考えることです。
たとえば、自社の強みや競争優位性を明確にしたいなら、SWOT分析やVRIO分析がおすすめ。これらは販売戦略の土台を築くために欠かせない、長期視点のフレームワークです。
逆に、商談現場でのヒアリングや提案の質を高めたいなら、SPIN話法やFABE分析、BANTなど、実務に直結する戦術系のフレームワークが効果的です。
また、「課題解決型営業を強化したい」「大型商談の受注率を高めたい」などの状況ベースの選定も有効です。複数の意思決定者が絡む複雑な案件ではMEDDIC、既存顧客へのアップセルならパレートの法則やバリュープロポジションキャンバスが機能します。
営業課題は事業フェーズや商材特性によって常に変化します。そのため、このフレームワークだけ使えばよいといった万能な答えはありません。
むしろ複数のフレームワークを組み合わせながら、課題・対象・フェーズに応じて柔軟に選び分ける運用力こそが、営業組織の競争力を左右するのです。
営業フレームワークのよくある失敗と対策

営業現場でフレームワークを導入しても、うまく機能しないケースは少なくありません。その多くは使い方の問題に起因しています。ここでは、よくある失敗例とその対策を紹介します。
穴埋めで終わる
営業企画の場で頻繁に起きるのが、3C分析やSWOT分析などを「とりあえず埋めるだけ」で満足してしまうケースです。
一見、戦略設計に取り組んでいるように見えますが、実際には思考停止したテンプレート作業で終わっている状態です。フレームワークの本質は、情報の整理ではなく、そこから戦略仮説や行動指針を導き出すことにあります。
たとえば、「競合が価格訴求型で自社は品質重視」と整理できたとしても、それを踏まえて「では、どの業種を狙うか?」「営業トークでどう表現するか?」まで設計してはじめて意味を持ちます。
対策としては、フレームワークを記入したら「次に取るべきアクションを必ず1つ書く」ルールを設けたり、ワークショップ後に戦術案を作成するところまでを一連の流れに含めると効果的です。
実態と乖離したフレーム活用
営業戦略をフレームワークで整理する際に、現実とは異なる理想像を無理やり当てはめてしまうことがあります。
たとえば、VRIO分析で「営業人材は価値ある資源」と結論づけたものの、実際は離職率が高く成果も個人差が激しい。こうした希望的観測による仮説では、戦略が現場に定着しません。
本来、フレームワークは仮説検証の出発点であり、願望の投影先ではありません。
現場のインタビューや営業データといったファクトベースのインプットを伴って初めて、意味のある分析が可能になります。実態との乖離を防ぐには、企画段階で「この内容は何を根拠に導き出したか?」と必ず検証する工程を入れ、事実と論理の接続点を明確にしておくことが重要です。
現場が参加していない
戦略設計を営業企画部門や経営層だけで進め、現場には完成品として共有するだけというパターンは、実行段階でつまずく典型例です。
なぜなら、現場の営業担当者がその背景や目的を理解しておらず、フレームワークが単なるお題として扱われてしまうからです。こうなると、戦略は実行されず、形骸化してしまいます。特に現場に対して十分な教育や育成が行われていなければ、理解の浸透はさらに難しくなります。
有効な対策は、初期段階から現場を巻き込むことです。その際、トップセールスや中堅層の意見をヒアリングするだけでなく、実際の業務制約や市場環境を十分に考慮することが欠かせません。
たとえば、営業全体でのワークショップ形式で共に戦略を設計することで、当事者意識と納得感を高められます。こうした取り組みは、現場に眠る改善の可能性を引き出し、従来のやり方にとらわれない新しい戦略の芽を生み出す契機にもなります。
営業フレームワークで属人化から脱却しよう
市場環境の複雑化や組織規模の拡大により、属人的な営業手法だけでは限界が訪れています。だからこそ、フレームワークを活用した戦略的な営業設計が重要なのです。
フレームワークを導入することで、誰が担当しても一定水準のアウトプットが出せる営業プロセスを構築できます。また、課題の構造化や提案の論理構築が容易になるため、商談の質と成果が飛躍的に向上します。
大切なのは、単にツールとしてフレームワークを使うのではなく、それを「共通言語」として組織に根付かせることです。
戦略設計から実行、振り返りに至るまでを一貫して支える思考の土台として活用すれば、営業は個人プレーからチームプレーへと進化していきます。
9Eキャリアで後悔のない営業職転職を
9Eキャリアは、営業職への転職に特化した転職エージェントです。営業未経験者にも対応しており、キャリアの棚卸しから書類添削、面接対策、検索では見つからない非公開求人の紹介まで一貫して無料で支援しています。
また、営業職への転職に特化した”求職者のことを1番に考える”伴走型転職エージェントです。
①“特化型”だからできる、他では出会えない厳選求人
②企業の裏側まで熟知したエージェントによる支援
③書類も面接も通過率が上がる、伴走型の転職支援
という特徴があります。
9Eキャリアの転職支援サービス
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
この記事の監修者
荒川 翔貴
学生時代に100名規模の営業団体を設立後、大手メーカーで新人賞、売上4,000%増を達成。その後人材業界に転身し、ベンチャー企業にて求職者・企業双方を支援。プレイヤーとして社内売上ギネスを塗り替えながら、3年で事業部長に昇進し組織マネジメントも経験する。
現在は株式会社9Eのキャリアアドバイザーチームリーダーとして、入社半年で再び社内ギネスを更新するなど、常に成果を追求し続けている。(▶︎詳しく見る)
