営業とマーケティングの違いとは?対立する理由や連携を深めるポイントを解説

「営業とマーケ、うちは全然うまくいってなくて…」
こんな言葉を、営業責任者やマーケ担当者から聞くことは少なくありません。
営業は「マーケが渡してくるリードの質が低い」と言い、マーケは「せっかく獲得したリードを営業がフォローしない」とこぼす。
成果を出すことが目的のはずなのに、なぜ両者は対立しがちなのでしょうか?
その背景には、役割、評価指標、時間軸といった、構造的な非対称性があります。つまり、対立は偶然ではなく、組織設計上の必然なのです。
本記事では、まず営業とマーケティングの本質的な違いを整理した上で、なぜ両者が対立するのか、どうすれば連携を深められるのかを徹底的に解説します。
部門間の対立を乗り越え、売上とLTVを最大化する連携型組織を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
9Eキャリアの転職支援サービス
9Eキャリアは、営業職の中でも将来性の高い職種に特化して転職支援を行っています。
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
営業とマーケティングの違いとは
営業とマーケティングは、いずれも売上の創出に直結する重要な機能です。しかし、その性質やアプローチは大きく異なります。
この違いを正しく理解していないと、「なぜマーケティングは成果が出ないのか」「なぜ営業は非効率なのか」といった相互不信に陥る原因となりかねません。
以下に営業とマーケティングの違いを表でまとめました。
| 項目 | 営業 | マーケティング |
| 対象 | 個々の顧客 | 市場全体 |
| 方法 | 対話・提案・交渉 | 広告・コンテンツ・イベント |
| 目的 | 契約を獲得 | 見込み客を育成 |
| 成果 | 受注 | 需要・関心の創出 |
営業は個客との接点で成果を生む役割、マーケティングは市場への働きかけによって機会を創出する役割と整理できます。
なぜ営業とマーケティングが対立するのか?

営業とマーケティングは、どちらも売上を支える重要な機能です。
しかし、現場では「両者がうまく連携できていない」と感じる人も少なくありません。とりわけ、リードの質や商談数をめぐって責任の所在があいまいになり、互いに非を押し付け合うような状況が見受けられます。
その背景には、両者の立場や役割の違いによって生じる、構造的なギャップが存在します。以下では、3つの観点からこの対立構造を読み解いていきます。
追うべきKPIが異なるため
営業とマーケティングでは、そもそも評価指標として注目する数値の性質が異なります。
マーケティング部門では、リードの獲得数やコンバージョン率といった統計的な母数や確率に基づく評価が中心です。一方、営業部門では、個別の商談ごとに勝敗や成約率が問われ、案件単位での成果が重視されます。
この違いにより、マーケティングが「多くのリードを獲得した」と成果を主張しても、営業は「質が低く商談につながらない」と反発する構図が生まれます。どちらも自部門のKPIに沿って主張しているため、議論がかみ合わず、平行線をたどることも少なくありません。
時間軸が異なるため
マーケティングは、中長期的な視点からリードの育成や認知の拡大を進めます。一方で営業は、月次や四半期といった短期の売上目標を追いかけます。この時間軸の違いが、両者の間に摩擦を生む要因となることは少なくありません。
たとえば、マーケティングが「半年後の商談化を見据えてリードを獲得した」と説明しても、営業は「今月のアポイントが足りない。すぐに面談可能な見込み客を回してほしい」と主張する場面が生じます。
こうした戦略と戦術のズレが続く限り、成果につながるリードの供給は難しくなります。
顧客データが断絶しているため
営業とマーケティングでは、活用するデータの性質にも大きな違いがあります。
マーケティングが重視するのは、GoogleアナリティクスやMA(マーケティングオートメーション)ツールによる、無記名かつ集団ベースの行動データです。一方、営業はSFA(営業支援システム)、商談メモ、録音記録など、個別の顧客情報に基づくデータを扱います。
この「集団 vs. 個別」「無記名 vs. 記名」といった情報の特性の違いが、両者の視点や判断基準のギャップを生み出します。
共通の顧客を対象にしているにもかかわらず、まったく異なるデータ環境で業務を進めている状態では、効果的な連携を図るのは難しいと言えるでしょう。
営業とマーケティングが連携するメリット

営業とマーケティングが対立関係から脱し、真に連携できるようになると、営業効率だけでなく、組織全体のLTV向上にもつながります。ここでは、連携によって得られる代表的なメリットを3つ紹介します。
商談の質と量を両立できる
営業単独では限界のあるリード獲得も、マーケティングと連携することで大きく広げることが可能になります。マーケティングが見込み顧客の数を拡大し、その中から営業が有望な案件を選び出して対応すれば、商談の質と量の両立が実現できます。
たとえば、ホワイトペーパーの提供やセミナーの開催を通じてスコアの高いリードを獲得し、それを営業がクロージングに集中して引き継ぐ体制を整えれば、営業活動の生産性は大きく向上します。
営業・マーケティング活動の再現性が高まる
営業が得た商談結果や受注に至った要因をマーケティングにフィードバックすることで、次回以降のリード獲得やキャンペーン設計に具体的な改善を反映できます。
逆に、マーケティングが実施した施策の効果について営業が商談の場で共有すれば、ターゲットに響くトークや資料の精度が高まります。
このように、施策と成果の因果関係が可視化されれば、偶然の成功ではなく、再現性のある仕組みとして営業・マーケティング活動を運用することが可能になります。
機会損失を減らせる
マーケティングと営業の連携が不十分だと、有望な見込み顧客を取りこぼしたり、適切なタイミングでアプローチできなかったりと、機会損失が生じやすくなります。しかし、明確なルールに基づいて情報共有を行えば、こうしたロスは大幅に削減可能です。
たとえば、関心度の高いリードに対して営業が即座にアプローチできる体制が整っていれば、商談機会を逃さず、コンバージョン率の向上も期待できます。また、確度が低い段階のリードをナーチャリングへ戻す判断も、両者の連携があってこそスムーズに行えます。
営業とマーケティングの連携方法

営業とマーケティングの連携を強化するには、単なる関係性の良好さだけでは不十分です。両部門が成果を共有し、継続的に業績を高めていくためには、具体的なプロセスとルールに基づいた仕組みが必要です。
ここでは、連携を構造的に推進するための5つのステップを紹介します。
STEP1:共通のKGI・KPIを定義する(評価軸の統一)
最初に取り組むべきは、営業とマーケティングの両部門で、最終的な目標(KGI)と進捗を測るための中間指標(KPI)を共通化することです。
たとえば、「売上1億円の達成」をKGIとして共有していれば、マーケティングはMQL(マーケティング資格リード)の数やコンバージョン率、営業はSQL(営業資格リード)からの受注率や商談件数といったKPIを、相互に連動する形で設計できます。
このように共通の指標を設定することで、両部門が別々のゴールを追う状態を回避でき、目標に向けた協働体制が築きやすくなります。
STEP2:リードの定義と評価ルールを統一する(SLAの策定)
営業とマーケティングの間で良いリードの定義に食い違いがあると、いくら数を供給しても成果にはつながりにくくなります。
その解決策として有効なのが、リードの条件や受け渡し基準を明文化する「SLA(サービスレベルアグリーメント)」の策定です。
たとえば、MQLの条件を「業種:製造業」「役職:課長以上」「スコア80点以上」「ホワイトペーパーをダウンロード済」と定め、営業側の対応ルールとして「24時間以内に初回接触を行う」「3回未接触であればナーチャリングに戻す」と合意しておくことで、両部門の判断基準と対応姿勢を揃えることができます。
STEP3:情報とツールを統合する
営業とマーケティングがそれぞれ異なるツールやデータベースを使用していると、情報共有の精度が下がり、連携が形だけのものになりかねません。
その防止策として重要なのが、MAとSFA/CRMを連携させ、顧客データを一元的に管理できる体制を構築することです。
たとえば、Web上での行動履歴、スコアリング結果、過去の接触内容などの情報を営業が事前に確認できれば、顧客の関心度やニーズを把握したうえで商談に臨め、提案の精度と成約の可能性が高まります。
STEP4:週次・月次での定例会を仕組み化
データやツールを整備しても、現場レベルでの相互理解がなければ、十分な効果は得られません。そのためには、週次や月次の定例会議を設け、営業とマーケティングが継続的に成果や課題を共有できる仕組みが欠かせません。
この際、単なる進捗報告にとどまらず、見るべき数字(例:CVR、受注率)や話すべき項目(例:施策の効果、ボトルネック)を明確にルール化し、会話の内容がKPI改善に直結するよう設計することが、連携の質を高める鍵となります。
STEP5:成果と失敗をナレッジ化・仕組み化する
成果を一時的なもので終わらせないためには、営業とマーケティングの両部門で、成功事例と失敗事例を共有し、再現可能な形で蓄積・活用していく必要があります。
たとえば、営業で有効だった資料やトークをマーケティングがコンテンツとして再構成したり、マーケティング施策で反応の良かった切り口を営業が提案時に取り入れたりすることで、成果の再現性を高められます。
ナレッジの共有とは、個人に属する経験や知見を組織全体の資産へと昇華させるプロセスです。これは、両部門の連携を継続的な成長につなげるうえで欠かせない取り組みです。
営業とマーケティングを連携するポイント
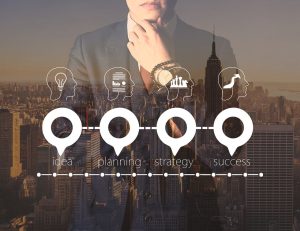
営業とマーケティングの連携を成功させるには、単にテクノロジーや施策を導入するだけでは十分ではありません。重要なのは、両部門の関係性や組織文化を踏まえたうえで、共通の認識と明確な役割分担を持つことです。
ここでは、連携を形だけのものに終わらせず、実質的な成果につなげるために押さえておきたい、2つの重要なポイントを解説します。
必ず共通のゴールを持つ
営業とマーケティングが異なる目標を追っていると、活動の方向性がずれ、連携は機能しにくくなります。
たとえば、マーケティングがMQL(マーケティング資格リード)の数を最大化することに注力し、営業が成約率を重視している場合、リードの質と量に対する認識がかみ合わなくなります。
このようなズレを防ぐためには、部門を越えてKGI(売上・受注件数・LTVなど)を共有し、その達成に向けてKPIを一貫性のある設計に整えることが不可欠です。
MQL → SAL(営業受入リード) → SQL(営業資格リード) → 受注というプロセスの各段階で、目標と責任範囲を明確に定義しておけば、部門間の連携は実行可能な仕組みとして機能します。
明確にリード定義をする
MQL(マーケティング資格リード)、SAL(営業受入リード)、SQL(営業資格リード)といった各ステージの定義が曖昧なままでは、リード評価が属人的になり、誤解や対立の原因となります。
そのためには、数値と行動条件に基づいた明確な評価基準を設けることが重要です。
たとえば、「製造業の課長職以上」「資料ダウンロード済」「スコア80点以上」といった定量的な条件を設定すれば、マーケティング側の供給基準と営業側の対応期待値を一致させられます。
さらに、営業側の対応ルールも「いつ・誰が・どのように・何を行うか」まで明記しておけば、業務フローが明確になり、部門間の衝突を未然に防げます。
営業とマーケティングの連携に効果的なツール

営業とマーケティングの連携をスムーズに進めるには、両部門が共通の顧客情報を見ながら活動できる環境の整備が欠かせません。
その基盤として有効なのが、CRM、SFA、MAといったツールの導入と連携です。
CRMは、顧客情報を一元的に管理し、営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど部門を越えた情報共有を促進します。たとえば、見込み顧客の基本情報、接触履歴、スコア、商談ステータスといった情報を一画面で把握し、部門間での情報の分断を防げます。
SFAでは営業活動の進捗や履歴を管理でき、MAでは見込み客の行動ログやスコアリングを可視化できます。これらのデータを連携させることで、ホットリードの抽出やナーチャリングの優先度判断がより的確になります。
これらのツールを個別に運用するのではなく、CRMを中核とし、SFAやMAと統合することで、営業とマーケティングがリアルタイムで顧客情報を共有し、施策全体の一貫性と実行精度を高めることが可能です。
営業とマーケティングに必要なスキル

営業とマーケティングは、共通の売上目標に向かって連携するべきパートナーであると同時に、それぞれ異なる専門性を担う役割でもあります。相手の業務を正しく理解することは、部門間の協働の質を高めるうえで欠かせません。
以下に、営業とマーケティングそれぞれの職種に求められる代表的なスキルを、簡潔に整理して紹介します。
営業に必要なスキル
営業は、顧客と直接向き合いながら商談を進め、受注という成果を獲得する役割を担います。そのためには、単に商品知識を持つだけでなく、対人関係や課題解決における実践的なスキルが不可欠です。以下は、営業に求められる代表的なスキルです。
・顧客とのコミュニケーション能力:相手の課題や要望を正確に引き出し、信頼関係を構築する力
・問題解決能力:顧客のニーズを明確化し、自社商材でどう解決できるかを論理的に導く力
・交渉力:価格や条件面での折衝を通じて、受注につなげるスキルは、BtoB営業において特に重要
マーケティングに必要なスキル
マーケティングは、市場全体を俯瞰しながら顧客の関心を喚起し、見込み客を創出・育成していく役割を担います。データと創造性を組み合わせ、戦略的に売れる仕組みをつくるには、以下のようなスキルが求められます。
・市場分析能力:顧客ニーズや競合動向、トレンドを的確に捉え、戦略に反映するためのリサーチ力
・データ解析能力:Web解析ツールやMAツールなどから得られるデータを読み解き、施策の改善に活かす力
・クリエイティブな発想:コンテンツ企画や広告コピー、キャンペーン設計など、顧客の興味を引く企画力
これらのスキルをお互いに理解し合い、強みを活かして役割分担を明確にすることが、真の連携強化につながります。
営業とマーケティングの違いを理解して連携を深めよう
営業とマーケティングは、企業成長を支える二つの推進力です。
しかし、役割や評価指標、時間軸、活用するデータの違いから、誤解や対立が生じやすいのも事実です。だからこそ、その構造的なギャップを理解し、共通のKGI・KPI、リード定義、情報連携の仕組みを整えることが、両部門を真に機能するチームへと導くポイントとなります。
営業が「売れる状況」をつくり、マーケティングが「売れる仕組み」を支える。
この両者が有機的に連携すれば、単なる受注件数の増加にとどまらず、LTVの最大化、商談の再現性向上、さらにはブランド価値の強化といった、持続的な成果につながっていきます。
もし今、営業またはマーケティングのどちらか一方に依存していると感じるなら、まずは小さな連携から始めてみてください。それが、事業全体を前進させる大きな一歩となるはずです。
9Eキャリアで後悔のない営業職転職を
9Eキャリアは、営業職への転職に特化した転職エージェントです。営業未経験者にも対応しており、キャリアの棚卸しから書類添削、面接対策、検索では見つからない非公開求人の紹介まで一貫して無料で支援しています。
また、営業職への転職に特化した”求職者のことを1番に考える”伴走型転職エージェントです。
①“特化型”だからできる、他では出会えない厳選求人
②企業の裏側まで熟知したエージェントによる支援
③書類も面接も通過率が上がる、伴走型の転職支援
という特徴があります。
9Eキャリアの転職支援サービス
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
この記事の監修者
荒川 翔貴
学生時代に100名規模の営業団体を設立後、大手メーカーで新人賞、売上4,000%増を達成。その後人材業界に転身し、ベンチャー企業にて求職者・企業双方を支援。プレイヤーとして社内売上ギネスを塗り替えながら、3年で事業部長に昇進し組織マネジメントも経験する。
現在は株式会社9Eのキャリアアドバイザーチームリーダーとして、入社半年で再び社内ギネスを更新するなど、常に成果を追求し続けている。(▶︎詳しく見る)
