営業がうまくいかない原因とは? 新規開拓営業がうまくいかないケースも合わせて対策やうまくいかせる方法を解説

営業がうまくいかない原因はさまざまです。たとえば、営業マン自身のヒアリング力をはじめとするコミュニケーションや対応に問題があるケースが少なくありません。原因が何であれ、営業がうまくいかないままでは困るため究明と対策が急がれます。この記事では新規開拓を独立見出しで分け、営業がうまくいかない原因と対策に加え、営業をうまくいかせる方法についても解説します。
9Eキャリアの転職支援サービス
9Eキャリアは、営業職の中でも将来性の高い職種に特化して転職支援を行っています。
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
営業がうまくいかない~本人に原因があるケース
営業がうまくいかない原因で本人に問題があるケースについて解説します。
ヒアリング力に問題がある
営業の仕事はトーク力が重要だと思われがちですが、トーク力を活かすにはヒアリング力が欠かせません。顧客、見込み客のニーズや課題を的確に把握するためには、細かい情報を不足なく引き出すヒアリング力を必要とします。
つまり、ヒアリング力に問題がある場合は必要な情報を引き出せず、顧客の課題を把握できないことから有効なソリューションの組み立てにつながらず、営業がうまくいかないという結果を招いてしまうのです。この状態でいくらトークを尽くしたとしても、顧客の反応は薄く、自分ばかりが喋っているという状況に陥りかねません。
売り急いでいる
営業マンは日々、目標とする売上・利益の数字を意識しながら仕事に励んでいます。順調に進捗しているときは良いですが、思うように数字が作れないときは焦る気持ちが先に立ってしまうこともあり得ます。売りたい気持ちが前面に出過ぎて顧客が引いてしまったり、必要な説明が十分でないままクロージングしようとしたりすれば、契約成立は難しくなるでしょう。
顧客との信頼関係が構築できていない
顧客との信頼関係が構築できていないと営業はうまくいきません。営業の仕事はさまざまありますが、基本的には個々の顧客と向き合うことで自社の商品・サービスを販売します。営業マンと取引する顧客は商材はもちろんのこと、営業マンへの信頼があればこそ商品・サービスの購入に踏み切るものです。
したがって、顧客との信頼関係を構築することが営業マンの重要な仕事だといえます。この過程が不十分だと、ほとんどの商談がうまくいかなくても不思議ではないでしょう。そもそも信頼関係ができていないためアプローチしても響かず、クロージングまで進みません。
会話のテンポがマッチしていない
営業マンと顧客の信頼関係構築の主要なツールとなるのが会話です。会話のテンポがマッチしていないとコミュニケーションが円滑に進まず、商品・サービスの販売という話にもなりにくいといえます。会話のテンポに違和感がある場合は、それが特定の顧客との間で起きているのか、多くの顧客で同じ状況なのかを確認する必要があるでしょう。
前者であれば相性の問題が考えられるため、より慎重に顧客を観察する必要がありそうです。後者の場合は自分の会話力の問題が浮かんできます。ロールプレイングや周囲のアドバイスを受けるなどして、会話がキャッチボールになるように訓練する価値はあるでしょう。
顧客の状況を考慮していない
ヒアリング力とも関連しますが、顧客の課題など状況がわかっていないまま、いきなりソリューションのプレゼンテーションを行っても営業はうまくいきません。また、状況がわかっているのに考慮しないで商談を進めても同じことです。営業がうまくいくためには、顧客が満足する必要があります。
押し売りになってしまっている
日本には「営業は断られた時から始まる」、「顧客の背中を押してあげるのが営業の役割」といったフレーズで育った営業が大勢います。ほとんどの営業マンは言葉の意味を正しく理解していますが、なかには勘違いしている営業マンもいるようです。
そもそもニーズがない顧客の断りに対して諦めないでプッシュし続けるなど、押し売りになってしまっているケースがあります。こうした売り方が癖になってしまうと、より営業がうまくいかない状況に陥ってしまいかねません。
スケジュール管理の失敗
できる営業マンはタイムマネジメントスキルが高いといわれています。逆に時間管理やスケジュール管理に失敗してしまう営業マンは、顧客に対してタイムリーな営業活動ができていないため、営業がうまくいかない状況になりがちです。また、約束の時間に遅れたり、失念してしまったりすれば信用をなくしてしまいます。
営業の進め方がわかっていない
営業マンの仕事に就くこと自体は誰でも可能です。資格や試験もなく、法人や個人の区別も関係ありません。そのため、営業マンのレベルは千差万別です。そもそも営業の進め方がわかっていないため思うような結果が出ない、営業がうまくいかないという営業マンがいても不思議ではありません。
どうせ売れないと思っている
営業の世界では、どうせ売れないと思っている商材が売れることは考えにくいといえます。
営業マンに必要な条件のひとつに、自社の商品・サービスに惚れるというものがあります。自分が良いと思わない商材を他人にすすめることはできません。よほどのことがない限り、どの商材にも良いところがあります。それを必要とする顧客とのマッチングは営業マンの仕事だといえるでしょう。また、自分が良いと思っていないだけで、商材自体は優秀ということもあります。
それでも自社の商品・サービスや自分自身に自信がなくて「どうせ売れないと思っている」なら、無意識に売れない行動に向かいがちになることから、その通りの結果になってしまいます。
クロージングが不十分
リードの獲得やリードナーチャリングがうまいのに、数字が上がらない営業マンがいます。原因は主にクロージング力です。といっても、問題なくクロージングまで持ち込む時点で営業マンとしての能力がないはずがありません。足りていないのは「顧客の背中を押してあげる」その最後のひと押しです。
自分ではやっているつもりでも、肝心なひと押しが抜けているため、結果につながらないのはもったいない話だといわざるを得ないでしょう。ひと押し多いかなと思うくらい、意識して押してみるとうまくいくかもしれません。
商談相手が決裁権者ではない
大企業相手の営業では上位役職者が出て来ずに、権限を持たない担当者レベルでのやり取りですべてが片付くこともあります。しかし、裏側では権限を持つ役職者による決裁が行われており、一般に決裁が下りるまで時間がかかる傾向が大です。そのため、決裁待ちであてにしていた商談が流れてしまい、営業がうまくいかないという事態も起こり得ます。そもそも決裁権者と会っていないため、結果がどうなるかわからないのが難点です。
営業がうまくいかない~本人以外に原因があるケース

営業がうまくいかない原因で本人以外に問題があるケースを解説します。
商材が競合他社より弱い
営業の努力に関係なく、商材の競争力が弱いため売りにくい商品・サービスも存在します。本人に原因があるケースで紹介した「どうせ売れないと思っている」ケースとは事情が異なり、あちらは自分で売れないと思っていることが原因ですが、こちらは商材自体の競争力の問題です。とくに競合製品が優秀な場合は苦戦を強いられることも多いでしょう。
その他
自社の対応が不適当だったために商談が頓挫するケースとして、営業マンの不在時にかかってきた顧客からの電話の扱いがあります。
・電話の受け答えに失礼があった
一般に会社員であれば電話の受け答えは無難にできるものですが、多忙なときなどに他社の電話と混同したり、保留にしたまま長く待たせてしまったりすることで、営業活動に悪影響を及ぼしかねません。
・電話がかかってきたことを伝言し忘れた
電話がかかってきたことを伝言し忘れるといったミスは誰にでも起こり得ることだといえるでしょう。顧客から電話があった事実を営業マンが知らないまま時間が過ぎてしまい、商談のチャンスを逃すケースもあります。
また、担当の営業マンでなければその顧客のことや商談の進捗などが何もわからないという仕組み、組織体制も営業がうまくいかない状況を作りやすい要因だといえます。営業マンがいないときや動けないときの対応力が乏しくなってしまうためです。
営業がうまくいかないときの対策

営業がうまくいかないときの対策について解説します。
原因を突き止める
まず、なぜ営業がうまくいかないのか原因を突き止めることが重要です。原因がわからないと対策の立てようがありませんが、原因を突き止めることで効果的な対策を打てる可能性が高まります。原因の多くは営業マン本人に起因するものであることから、原因究明には営業活動における顧客との接し方を振り返ることが欠かせません。
リサーチを徹底する
原因に対する施策と同時に、顧客に関するリサーチも重要です。ヒアリングで収集する顧客情報だけでなく、さまざまな媒体を利用した情報収集も効果があります。顧客そのものや顧客の業界など関連する事柄も含めて事前リサーチを徹底することにより、顧客の信頼を得る下地ができ、円滑な営業の流れを作ることが可能です。
コミュニケーション能力を磨く
ヒアリング力の問題や会話のテンポのミスマッチなど会話の根本的な部分で対策が必要なケースでは、コミュニケーション能力全般を磨くことが重要です。また、営業がうまくいかないケースだけでなく、コミュニケ―ション能力の向上は営業に必要なことであり、普段から意識してスキルアップに取り組みましょう。
聞き役に徹して信頼関係を深める
人は自分を重視して話を聞いてくれる相手には良い印象を持つ傾向があります。会話のなかで聞き役に回ることで「話し上手は聞き上手」を実現することが可能です。顧客の状況把握や課題の引き出し、顧客の意向確認が不十分であると感じるなら、これまで以上に聞き役に徹する意識を持ちましょう。顧客が話したいことを話せる状況を作ることで、信頼関係を深めることができます。信頼関係が深まることで、営業がうまくいかない状況の解消が見込めるでしょう。
セルフイメージの向上
セルフイメージ、自己評価を向上することで、自信を取り戻して堂々と営業活動に励むことができます。顧客から見ても自信のなさが消えることで安心感が芽生えるでしょう。そのためには成功体験を思い出すなどのイメージトレーニングや、営業研修、外部セミナーへの参加などのアクションが有効です。
営業研修や外部セミナーは基本的な営業の進め方の確認にもなり、クロージングやスケジュール管理も含めた営業がうまく行かない原因の多くに対応可能です。
決裁権者を確認する
リード対応では決裁権者の確認が欠かせません。決定権を持つ人が誰なのかを確認することにより、通常時に顔を合わせることがなかったとしても、担当者を通じて挨拶の機会を得る努力が必要です。決裁権者がわかっていれば、常にそちらを意識することで商談の進め方の工夫にも役立ちます。ただし、担当者をないがしろにしないよう注意が必要です。
商品を完全に理解する
競合他社の製品に対して弱い自社の商品・サービス自体を営業が変えることはできません。しかし、商品を完全に理解することで、新しいアプローチ方法が浮かんでくることもあります。また、競合に弱いという判断が営業マンの思い込みである場合は、理解を深めることで本当の価値に気が付くなど、有効な対策になり得ます。
行動を変える
今の行動でうまくいかない以上、イメージトレーニングとは別に行動を変えることが有効な対策になり得ます。その際に参考になるのが成功したケースです。成功事例に学び、アプローチその他の行動を当時のように変えてみるなど工夫してみます。
うまくいっている人の真似をする
成功事例が参考になる様に、うまくいっている人がやっていることも大いに参考になります。うまくいっている人はそのやり方で結果を出しており、真似をすることで自分もうまくいく可能性が高くなるでしょう。
属人化の個人プレーから情報共有のチーム営業へ
社内の対応がまずいケースや担当営業マンがいないと対応が後手に回るといったケースでは、営業の属人化が起きてしまっています。属人化は個人プレー重視の営業につきものといえるため、情報を可視化・共有し、チーム営業へと移行することが有効な対策です。
新規開拓営業がうまくいかない原因と対策
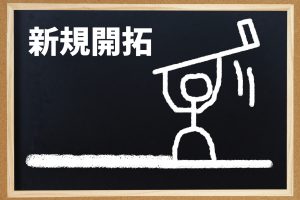
営業のなかでも新規開拓営業には特有のうまくいかない原因が考えられます。対策とともに紹介しましょう。
やみくもに訪問・架電している
新規開拓営業にはどうしても数を撃つ傾向があります。そのため、手当たり次第にアプローチを行うといった非効率な活動も見受けられ、労力の割に報われないケースが出てしまうようです。やみくもに訪問・架電しても成果にはつながりにくいため、対策としては商材にマッチするターゲットの選定をしっかりと行い、戦略的なアプローチを行うことが大切になります。
基本的に断られる
飛び込みに代表される新規開拓営業は、何の接点もないところからスタートするため基本的に断られるものです。情報を出してくれないどころか、ヒアリングしようにも会話すらしてもらえないケースも珍しくありません。名刺交換ができれば良いほうです。
とはいえ、ターゲットの選定が間違っていなければ、応酬話法や顧客のメリットを正しく伝えるトークスクリプトの作成、PDCAを回しながらのロープレの繰り返しなどの準備や対策により、リード獲得につながっていくでしょう。
営業マンが新規開拓に不慣れ
新規開拓に慣れていないと効率よく回れなかったり、厳しい断り文句に凹んだりしてしまいます。対策としては、新規開拓を得意とする先輩からアドバイスを受ける、先輩の営業に随行する、同行営業してもらうなどです。社内の成功者から学ぶだけなら無料ですぐにできます。
メンタル面の対策としては、慣れる、気分転換する、誰かに愚痴を聞いてもらう、割り切るといった対症療法的なものとなります。顧客の言動をコントロールすることはできません。ただし、こちらの接し方に気を付けることで、顧客の反応が多少は改善する可能性があります。
目標達成イメージや自分のメリットを重視しモチベーションを維持
営業がうまくいかない状況が続くと嫌になってしまうことがあるのは、人間である以上仕方ありません。重要なことはその際の対処法です。目標達成イメージを膨らませたり、インセンティブなどのメリットを考えることでモチベーションキープを図ります。
営業をうまくいかせる基本は顧客に選ばれる営業マンになること

営業をうまくいかせるコツ、基本的な考え方は自分が顧客に選ばれる営業マンになることです。
営業がうまくいかないのは自分が選ばれていないから
営業はモノを売るのではなく自分を売るともいわれているように、多くのケースで商品・サービスとともに営業マン自身が選ばれています。したがって、営業がうまくいかないのは顧客が自分(という営業マン)から買いたい・話を聞きたいと思っていないためです。仮に競合他社に負けた場合、商材自体の競争力を別にすれば、顧客がライバルの営業マンを選んだということになるでしょう。
とはいえ、顧客も企業である以上、経済的な大きな損をしてまでライバルから買う判断はしにくいことから、営業マンを選ぶのは主に他の条件が拮抗しているときに多くなりそうです。ただし、ケースによっては他の条件が不利でも営業マンへの信頼が勝って選ばれることがあります。
営業に必要なスキルを磨く
顧客に選ばれる営業マンになるためには、前提として営業に必要なスキルを磨く必要があります。スキル不足の営業マンではスタートラインに立てないかもしれません。必要なスキルにはコミュニケーション、ヒアリング、ロジカルシンキング、課題発見・分析、プレゼンテーション、ストレス耐性、トラブル対応などがあり、顧客の信頼を得る営業活動を遂行するために欠かせないスキルです。
人となりを見られている
専門性やスキルを備えた状態で顧客の役に立とうと寄り添う姿勢を通じて、営業マンとしての人となりを見られています。重要なことは嘘をつかない、約束を守る、曖昧な情報を伝えない、誠心誠意の対応をわすれないなどです。顧客の信頼を得るまでの道程が長かったとしても、失うのは一瞬であることを肝に銘じる必要があります。
営業をうまく進めるためのトークプロセス

営業をうまく進めるためにはトークプロセスが重要になります。トークプロセスとはアイスブレイク、ヒアリング、プレゼンテーション、クロージングと進むトークの流れのことです。
最初は自然に会話が続くことを目標としたトークを
セールストークといっても、商材を売り込む話ばかりをするわけではありません。初めは良好な関係性を築いていないため、商材の話をしても効果が薄いことから、まずは自然に会話が続くことを目標にします。話題は天気など無難なもので警戒心を解くことが重要です。
信頼関係を構築する
回を重ねることで顧客を理解するだけでなく自分を理解してもらい、信頼関係の構築を目指すトークを行います。
徐々に本題に入る
お互いにいつまでも世間話というわけにはいきません。徐々に本題に入りヒアリングを進めます。顧客の反応が薄ければ関係性が深まっていないと判断できます。引き続き信頼関係構築を行いながらヒアリングトークを繰り出しましょう。ヒアリングにはできる限り多くの時間を使って、必要な情報を漏れなく引き出します。
顧客の課題解決に役立つ情報の提供
具体的なソリューションの紹介も含めて、顧客の課題解決に役立つ情報提供を行います。顧客の反応を見ながら、本格的なプレゼンテーションのタイミングを図りましょう。
プレゼン~クロージング
常に顧客ニーズを確認しながら、課題解決に最適なソリューションを提案します。プレゼンテーションでは顧客の導入メリットなど、顧客が知りたい情報を漏らさずに伝えることが重要です。顧客の反応を見ながら顧客ファーストのトークでクロージングに持ち込みます。
フォロー
クロージングの成功・失敗にかかわらず、フォローをしっかり行います。ここでのトークがしっかりできていれば、商機の拡大も不可能ではありません。逆に気を抜いてしまうと、これまでの苦労が水の泡になりかねません。たとえクロージングが成功だった場合でも、次の商機を失うおそれがあります。
営業をうまくいかせるITツールの活用

ITツールの活用は営業をうまくいかせるために欠かせないポイントです。
CRM
CRMは顧客関係管理と呼ばれる顧客管理システムです。顧客情報の一元管理による情報共有と素早い顧客対応など、属人化からチーム営業に移行する営業現場に役立ちます。部門間の連携強化にも適したITツールです。
SFA
SFAは営業支援システムで、報告書の作成や営業プロセスの可視化と進捗管理など、商談のサポートに威力を発揮します。また、営業部門のレベル均一化に役立つナレッジ共有にも便利なITツールです。
MA
MAはマーケティングオートメーション(マーケティングの自動化促進)システムで、コンテンツ配信やリードセグメンテーション、リードナーチャリングを効率よく行える支援ツールです。
営業がうまく行かなくても焦りは禁物

営業がうまくいかないと気持ちに焦りが生じやすく、焦りはミスを呼び、ミスが焦りを呼ぶ悪循環に陥る恐れがあります。営業に焦りは禁物です。
数字を意識し過ぎない
営業マンは数字を抱えており、売上・利益の目標を達成する任務を背負っているためプレッシャーも強く、数字を意識するあまり、強引な売り込みになってしまうことが起こり得ます。その結果、顧客が離れるなどの逆効果が生じかねません。焦りにつながる数字を意識し過ぎないことが重要です。
顧客のために提案する
営業の成果はあくまでも顧客のために提案した結果だと考え、顧客ファーストの営業を実行することで、目先の数字に惑わされることによる悪循環を避けることが可能です。事実、顧客満足を得られれば、アップセルやクロスセル、増設やリプレース、関係会社の紹介などビジネスチャンスが広がります。
冷静な分析が重要
焦る気持ちが強くなると状況の客観的な判断がしにくくなります。パニック状態になる前に、焦る気持ちをぐっと抑えて、冷静に状況の分析を行うことが必要です。現状を正確に把握することで、やるべきことは焦りではないと気付けるでしょう。
営業職の転職で焦らないために
営業がうまくいかなくて焦る前に、営業職の転職がうまくいかなくて焦っているとすれば、おすすめの解決策は専門家の支援を受けることです。営業職の転職に特化した9Eキャリアなら、焦りとは無縁の転職活動を進めることができるでしょう。
営業がうまくいかないときは冷静に原因を探って対策をとろう
営業は成果に波のある仕事であり、簡単に安定した結果を出せる仕事ではありません。うまくいかないと焦ってしまいがちですが、焦っても成果が出るわけではなく、うまくいかない状況が悪化するおそれがあります。軌道修正したいなら、うまくいかない理由を考え、原因に応じた対策が必要です。そのためには、冷静になってうまくいかない原因を探ることから始めましょう。
9Eキャリアで後悔のない営業職転職を
9Eキャリアは、営業職への転職に特化した転職エージェントです。営業未経験者にも対応しており、キャリアの棚卸しから書類添削、面接対策、検索では見つからない非公開求人の紹介まで一貫して無料で支援しています。
また、営業職への転職に特化した”求職者のことを1番に考える”伴走型転職エージェントです。
①“特化型”だからできる、他では出会えない厳選求人
②企業の裏側まで熟知したエージェントによる支援
③書類も面接も通過率が上がる、伴走型の転職支援
という特徴があります。
9Eキャリアの転職支援サービス
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
この記事の監修者
荒川 翔貴
学生時代に100名規模の営業団体を設立後、大手メーカーで新人賞、売上4,000%増を達成。その後人材業界に転身し、ベンチャー企業にて求職者・企業双方を支援。プレイヤーとして社内売上ギネスを塗り替えながら、3年で事業部長に昇進し組織マネジメントも経験する。
現在は株式会社9Eのキャリアアドバイザーチームリーダーとして、入社半年で再び社内ギネスを更新するなど、常に成果を追求し続けている。(▶︎詳しく見る)
