営業ヒアリングのコツとは? 顧客ニーズなどの情報を引き出す流れやフレームワークも紹介

営業のヒアリングは最終的な売上・利益につながる重要なプロセスです。ヒアリングの現場ではタイミングを見計らってコツを使うことで必要な情報を引き出しやすくなります。
この記事では、営業のヒアリングで役立つコツに加えてヒアリングの役割や流れ、注意点を解説するとともにフレームワークも紹介します。
9Eキャリアの転職支援サービス
9Eキャリアは、営業職の中でも将来性の高い職種に特化して転職支援を行っています。
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
営業に不可欠なヒアリング
ヒアリングとは英語の「hearing」がカタカナ語化して広く使用されている言葉です。一般に意見や希望、状況などを聴き取ることや聴取の場面を指しており、ビジネスの現場でも耳慣れています。営業におけるヒアリングは主として見込み客や既存顧客などを対象に行われているといえるでしょう。
ヒアリングが営業の成否を決めるといっても過言ではない
営業にとってヒアリングは不可欠なプロセスです。主としてプレゼンテーションの前までに行われるものの、営業プロセスのどの段階でも必要な要素となっています。営業が行うコミュニケーションのなかでも重要で、ヒアリングの出来不出来が商談・契約の成否を決めるといっても過言ではありません。
顧客の情報を深掘りするヒアリング
ヒアリングが不可欠な理由は顧客情報を深掘りする点にあるといえます。基本的な顧客情報のヒアリングで終わってしまえば、営業を進めるうえで必要な情報を得にくくなってしまいます。顧客が話す内容から引き出したい情報を探る、より深い情報を引き出す点がヒアリングの肝です。
ヒアリングの目的

ヒアリングの目的を端的に表すなら、営業を進めるうえで必要な情報を得ることだといえます。具体的には以下に示す3点が大きな目的です。
顧客の現状を把握する
ヒアリングの目的のひとつは、顧客の現状を正確に把握するための情報を引き出すことです。現状として把握すべき内容には以下のような項目があります。
・会社の基本情報
・事業内容と取り組みの状況
・決裁権者と決裁システム
注意したいのは、基本情報や事業内容などはヒアリング前の準備段階で集めておくべき情報だという点です。なぜなら、何も知らない状態でヒアリングに臨んでしまえば、やる気も含めて相手の不信を招くおそれがあるからです。調査した内容の確認や、補足的な質問をすべきだといえるでしょう。
顧客ニーズと課題解決のヒントを引き出す
営業のヒアリングで最重要といえるのが顧客ニーズと課題解決のヒントを引き出すことです。顧客が何に困っていて何を求めているのか、顧客自身が気付いていない潜在的な課題はあるのか、課題解決のために何が必要なのか、自社のソリューションがマッチするのかなど、その後のリードナーチャリングやプレゼンテーションにつながる情報を引き出します。
ライバルの情報も探る
直接的なニーズとソリューションの話だけでなく、競合他社の食い込みについての情報を引き出し、対策を立てることもヒアリングの大きな目的です。他社の動向に気付かないままでいると、「あの話はA社に決まったよ」などという事態が起こりかねません。逆にしっかりとしたヒアリングができていれば、ライバルに差をつけることもできます。
それぞれの関係性にもよりますが、他社が動いているという事実だけでなく、どのような提案がなされているのか、どの程度まで話が進んでいるのかといった細部までヒアリングしたいものです。
関係構築もヒアリングの役割

ヒアリングには事務的で形式的な作業もありますが、営業のヒアリングはその目的からわかるように簡単なものではありません。高いレベルでのコミュニケーションが必要なプロセスです。コミュニケーションはキャッチボールであり、言葉・情報というボールをうまくやりとりできるから続くものであり、的外れな言葉・情報のやり取りでは続きません。コミュニケーションとしてのヒアリングが続かなければ、目的を達することもできないでしょう。
しっかりと準備を行ったうえで、ヒアリングという名のコミュニケーションを成立させることで、顧客との信頼関係を構築する。それもヒアリングの目的のひとつです。
ヒアリングといえば聞く側と聞かれる側に分かれた場面を想像しやすいかもしれません。そのため、聞く側が一方的に評価を行い、感想を抱くといった勘違いが起こりやすくもあります。しかし、コミュニケーションであるヒアリングの現場では、聞く側だけでなく聞かれる側も相手を見ている点に注意が必要です。
つまり、営業のヒアリングにおいては、顧客も営業を見ている、値踏みしているといえます。ヒアリングが低レベルだと感じられれば、深掘りは難しく良好な関係の構築も期待薄になりかねません。
ヒアリングの質を左右する大きな要素が事前準備です。準備には回答の内容に応じた進め方の想定も含みます。「ヒアリングは相手の回答次第だから準備をしても仕方ない」といった声もあるようですが、ヒアリングこそ入念な準備が必要なプロセスだといえます。
ヒアリングの結果次第では営業中止を考える

ヒアリングは営業を成功させるために行うものです。したがって、質問への回答を想定し、商談につながる情報を引き出す工夫が求められます。とはいえ、すべての顧客が商売の相手になるとは限りません。営業といえば、砂漠で靴を売るエピソードなどが訓話としてよく知られていますが、潜在的なニーズがあればともかく、まったくニーズのない相手もいれば、ニーズが生じるまでに時間が必要な相手もいます。
限られたリソースの有効活用が求められる営業の現場においては、ヒアリングの結果次第で営業を中止する考えも必要です。
営業が行うべきヒアリング前の準備
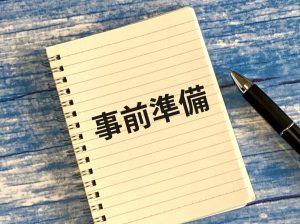
営業のヒアリングそのものは顧客との間で行われるものですが、すでに述べたように顧客と向き合う前の準備が重要なプロセスです。
情報収集
相手のことを何も知らないでヒアリングに臨むことは、顧客に対して失礼だといえるでしょう。やる気のなさとして感じとられるかもしれません。もちろん、ローラー作戦のような飛び込みセールスであれば事前の情報収集を抜きにして行うケースがないわけではありません。
とはいえ、2025年現在の営業では、飛び込みであっても可能な限り事前の情報収集を行うケースが多いといえるでしょう。
情報収集の主な手段は以下の通りです。顧客に関する情報を可能な限り多く集めて、ヒアリングしやすいように整理しておくことが求められます。
・公式サイトやSNSなど顧客のオウンドメディア
・報道や口コミ
・業界・市場動向
・過去の取引 など
仮説を立てる
仮説を立てることはヒアリングを有効なものとするために重要な事前準備です。事前に集めた情報をベースに課題を想定します。
業界や企業規模、市場動向などを踏まえてどのような課題を抱えていそうか仮説を立てるのです。その課題に対するソリューションについても考えておきましょう。
ヒアリングの現場では、仮説を検証する作業を行います。仮説が正しければソリューションの提案に結びつけやすいといえます。仮説が外れていたとしても、具体的な仮説を投げかけることで、本当の課題など欲しい情報を引き出しやすくなるでしょう。
質問の準備
仮説の検証は当然ですがヒアリング中の質問で行います。したがって、仮説に沿った目的達成までの質問の準備が重要です。可能な限り想定問答を作成し、流れの確認をしておくと円滑に進む可能性が高まります。
営業におけるヒアリングの基本的な流れ

営業において一般的に行われているヒアリングの基本的な流れについて解説します。
導入・あいさつ
営業マンに限らず、初対面の相手と会うときは第一印象が重要です。まずは社会人、営業マンとしてふさわしいマナーを守ったあいさつから始めます。
アイスブレイク
営業マンが来る、営業マンと会うとなれば、多くの人は売り込みが頭に浮かぶでしょう。企業の担当者であっても同様で、程度の差こそあれある種の警戒感を持っていると考えます。仮に警戒感がなかったとしても、顧客自ら欲しいものを買うために商店などに出向いているわけではないため、「いきなり本題に入られても話すことはない」といった反応になったとしても不思議ではありません。
最初のあいさつが終わったら本題に入る前に、軽い話題でやりとりすることで緊張をほぐす「アイスブレイク」を前置きします。
・業界のホットなニュース
・趣味
・天候や近所の話題
・顧客企業に対する親近感を示すエピソード
商談とは直接的な関係のない話題から入ることにより、警戒心や緊張感をほぐし、本題のヒアリングがしやすい状況を作り出します。とはいえ、できる範囲で次につながる話題を選ぶことも忘れないようにしましょう。たとえば、共通の趣味の話なら親近感がわいて話を進めやすくなったり、次回のアポが容易になったりします。
アイスブレイクをどの程度とるかはケースバイケースです。時間がないときは簡単に切り上げないといけないケースもあるでしょう。
課題の聞き取り
課題の聞き取りでは事前準備で用意した質問や、回答を受けてその場で考えた質問を的確に投げかけます。表面的な話の段階とは異なり、深掘りの際にはより繊細な注意が必要です。深掘りすればするほどピンポイントの細かい話になるため、少しズレただけでも無駄な質問や不適切な質問になってしまうおそれがあります。また、無遠慮に踏み込むような質問にならないよう配慮も必要です。後述する「欠かせない確認事項」も忘れずにチェックしましょう。
顧客の役に立ちそうな情報提供
ヒアリングを成功させるためには、顧客の役に立ちそうな情報提供が欠かせません。単に質問と回答をするだけでは、顧客としてはメリットを感じられないヒアリングになってしまいます。同じパターンが続くと、「なんでわざわざ回答しなければならないのか」といった不満にもつながり得ます。情報提供の具体例としては、業界の動向トレンドや課題解決に役立つ自社のソリューション紹介、同種の案件で課題解決に成功した事例の紹介などです。
反応の確認
顧客の役に立ちそうな情報を提供したなら、必ず顧客の反応を確認します。情報を提供しただけでその話を終わらせてしまってはチャンスを見逃すことになりかねないためです。反応を確認して、話を展開させることでさまざまな情報を引き出すことができます。また、関係構築にも役立つでしょう。
ソリューションの提案
顧客の反応次第では、単なる紹介ではなくソリューションの提案を行います。ただし、迷うようならヒアリング段階ではあくまでもこういったソリューションがあると告知する程度にとどめる方が無難です。そこまで乗り気になっていない顧客に対して強く打ち出し過ぎると、薄れていた警戒心が強まってしまうおそれがあります。もちろん、話の進み方によってはヒアリングで終らずにそのまま本格的なプレゼンテーションに移行してクロージングまで持ち込むことも可能です。
疑問点などの確認
ここまでのヒアリングで顧客が抱いた疑問点などを確認することが重要です。その目的は、顧客の正確な理解を助けて商談につなげることであったり、残っていた警戒心を消して信頼関係の構築を進めることであったりします。ソリューションについても同様で、疑問点がなくなれば導入への意欲も高まるでしょう。疑問点がなくなることによりクロージングまで一気に進むことがありますが、そういったケースもあるという例であり、拙速な判断で先を急ぎ過ぎない慎重さも必要です。
アポ獲り
予定していたヒアリングが完了した段階でクロージングする状況ではない場合、単に「今日はこの辺で」と終ってしまっては顧客の熱が冷めてしまいかねません。断られたら仕方ありませんが、次回のアポを獲っておくことはヒアリング現場の最後の作業として必須です。
アポ獲りは何月何日何時という具体的な日程が前提となります。そこまで決められない場合でも、来週の後半やいつまでにアポの連絡を入れるなど「約束」といえる状態が必要です。また今度会いましょうなどという話では社交辞令になってしまい、アポとは呼べません。
次回の準備
ヒアリング先から帰ってきてもまだ終わりではありません。ヒアリング内容を整理して分析する必要があります。営業中止の判断をした場合以外は、ヒアリングが不足している点やプレゼンテーションの準備など、次回に向けた仕事が不可欠です。
また、状況に応じた顧客フォローも考えられます。昔ながらの営業手法としては面会へのお礼状などがありますが、現代ではお礼のメールもひとつの方法です。単にお礼だけではインパクトが薄いと感じる場合は、疑問点に対する回答の補足を添付する手もあります。
営業のヒアリングで欠かせない確認事項

営業のヒアリングにおいて引き出す情報で、課題の聞き取りや疑問点などメインと呼べる項目以外の確認事項について解説します。現状把握や課題解決、ソリューションの提案を支えるために欠かせない情報の確認であり、事前に入手している場合を除いて忘れてはならない一般的な確認事項です。
予算
課題解決に出せる予算がどのくらいの規模感なのかを確認することは、ソリューションの提案と売上見込みにかかわる重要な作業です。予算込みで課題が上がっている場合はわかりやすいですが、課題中に予算が上がっていない場合や課題が潜在的で予算の組みようがない場合には、別途想定を交えて細かくヒアリングする必要があります。
スケジュール感
課題解決までのスケジュール感の確認は、売上の計上時期や納期にかかわるため外せない確認項目です。スケジュール感の把握に失敗すると、営業活動の優先順位を間違えることにつながりかねません。商機が熟していない案件を優先してしまうことで、その間に別の案件を失注したり、押し売り感が強くなって優先した案件まで頓挫したりしかねません。
決裁権者
小規模な会社であれば社長が個別案件の担当者というケースが少なくありません。そのため、営業マンとしては話が進めやすく直接的には社長だけを相手に商談を行えば良い話になります。しかし、社長以外が担当者である場合は決裁権者の確認が必要です。また、担当者の裁量権の範囲を確認することも忘れてはならないでしょう。ただし、確認の際には担当者に失礼にならないよう注意する必要があります。
また、他にキーパーソンがいないかを探ることも重要です。会社によっては社内外の第三者的な人物の意見が結果を左右するケースがあります。そのような人物が存在する場合は、行き過ぎにならない程度にコネを使うなどアシストを求めることも営業活動の一手です。
手続きの流れ
決裁の手続きがどのように流れるのかも、商談の進行に影響するため確認したい項目です。担当者が導入の意思を持ったとして、最終的な決裁権者の判断が下りるまでどの程度の時間がかかるのか、その流れがわからないと、売上の予定や納品の準備が進みません。
営業ヒアリングを成功させる5つのコツ

営業ヒアリングには事前準備や現場での手順・注意事項とは別に、成功のコツ、テクニックが主に5つあります。
話し上手は聞き上手
話し上手は聞き上手とは、会話の基本として広く知られている事柄です。日常会話であれビジネスシーンであれ、有効なコミュニケーションは相手の話をしっかり聞くことからはじまるといえるでしょう。相手の話を聞くこととはまさにヒアリングであり、相手目線で会話を進めることが重要です。
人は自分の話を聞いてくれる人には深い話をしようと思えます。しかし、喋るばかりで聞いてくれない相手に大事な話をしようと思う人は多くないでしょう。
営業マンは口が達者で喋ることが好きだという思い込みは少なくないようですが、喋ることが好きであっても自分ばかりがベラベラ喋っていてはヒアリングになりません。そもそも、営業マンは口が達者である必要もなく、的確なコミュニケーションを取れるか否かが問題です。程度問題ではあるものの、喋るよりも聞く方が好きだという人のほうが営業マンに向いているともいえます。
当然ですが、営業マンが喋るのを控えて顧客が話す量が多ければ良いというわけではなく、お互いが必要な分をしっかり話すことが重要です。話す内容も重要で、顧客に話を振っていたとしても、顧客に関係のない話をさせていたのでは逆効果になってしまうでしょう。質問の言葉もわかりやすさを心がけます。
ペーシングを意識する
会話には心地良い会話とそうでない会話があります。話す速度、声の大きさ、喋り方や呼吸は人によって異なるため、営業マンと顧客の組み合わせによっては、自分のペースとかけ離れていて苦痛を感じる会話になる可能性を否定できません。営業マンが会話のペースを相手に合わせることでコミュニケーションがスムーズとなり、ヒアリングの成果が期待できます。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分ける
質問の形式にはオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンがあります。オープンクエスチョンとは、「この件で困っていることを具体的に教えてください」「どのような機能があればより有効に使えますか?」といった、自由な表現での回答を求める質問です。クローズドクエスチョンは、「この件で困っていることがありますか?」「欲しい機能は以下の3つのうちどれですか?」といった質問で選択肢を用意します。
詳細な情報を引き出す場合はオープンクエスチョンを、あらかじめ絞った回答が欲しい場合はクローズドクエスチョンを用いての使い分けが重要です。
質問の切り口を変える
質問の切り口、仕方を変えることで曖昧だった回答が明確になることもあります。意図した回答を得られないケースがあるのは、質問が雑だったり質問の捉え方が人によって異なることが主な原因です。簡単な質問では必要ないかもしれませんが、ヒアリングにあたっては、同じ質問を異なる表現に言い換える準備をしておくと良いでしょう。
フレームワークやヒアリングシートの活用
漏れのない的確なヒアリングを行うには、フレームワークやヒアリングシートの活用が望ましいといえます。頭の中に叩き込んでいたとしても、ヒアリングは生き物であり状況によっては予定通り進まず、混乱してしまうこともあると考えられるためです。
営業ヒアリングので役立つフレームワーク
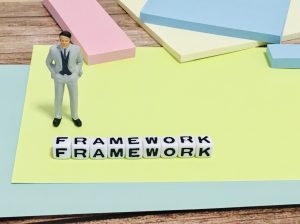
フレームワークは営業ヒアリングを成功させるために利用されているコツのひとつです。主なフレームワークに以下の4つがあります。
SPIN話法
SPIN話法とは、以下の質問項目の頭文字をとったヒアリングのフレームワークです。
1.Situation(状況質問)
2.Problem(問題質問)
3.Implications(示唆質問)
4.Need-Pay off(解決質問)
SPIN話法は現状の体制や利用サービスなどの把握から顕在・潜在ニーズや問題のあぶり出しと解決の必要性の共有、課題未解決のデメリット・課題解決によるメリットと必要なソリューションの認識といった流れを作ります。
5C分析
5C分析とは3C分析と呼ばれる分析法を拡大したもので、本来は自社の現状把握などの分析に用いられる方法ですが、ヒアリングのフレームワークとしても有効です。以下の5つの項目についてヒアリング・分析します。
1.Customer(顧客や市場)
2.Company(会社)
3.Competitors(競合)
4.Customer’s Customers(顧客の顧客)
5.Customer’s Competitors(顧客の競合)
顧客だけでなくその先にいる顧客の顧客にもスポットを当てています。
5C分析には、1〜3が同じで4と5が異なる分析法もある点に注意が必要です。
4.Collaborator(中間顧客や協力者)
5.Community(地域)
BANT情報
BANT情報は、最初に行う顧客ニーズのヒアリングと営業のヒアリングで欠かせない確認事項をフレームワークとして整理したものです。
1.Budget(予算)
2.Authority(決裁権者)
3.Needs(顧客ニーズ)
4.Timeframe(導入時期)
顧客ニーズは営業マンの頑張り次第で高まるともいえますが、まずはニーズの有無、そのレベルをヒアリングすることが必要といえます。BANT情報のヒアリングで注意すべきは、ただアリかナシかを問う質問をしても、初回で関係性が構築されていない間柄では回答を得られない可能性が高い点です。
たとえば、「ご予算はいくらをお考えですか?」とストレートに質問しても、曖昧に濁されるおそれがあります。「この場合だとこのくらいの費用になることが一般的ですが、コスト感としていかがでしょうか?」のように質問すれば「ちょっと高いね」といった回答が得られる可能性が高くなるでしょう。
MEDDIC
MEDDICは見込みの確度を見極めるためのヒアリングフレームワークです。
1.Metrics(測定指標)
2.Economic Buyer(決裁権者)
3.Decision Criteria(意思決定基準)
4.Decision Process(意思決定プロセス)
5.Identify Pain(課題)
6.Champion(擁護者)
測定指標はソリューションに期待する効果・収益を示します。2以降はBANT情報でも扱う項目ですが、より具体的な選定基準や別のキーマンなどが含まれるフレームワークです。
営業のヒアリングシート

フレームワークを理解してヒアリングすべき内容を頭に叩き込んでいたとしても、実際に顧客を前にしたやりとりを行うなかで、適切な質問が円滑に出てくるとは限りません。ヒアリングに自信がない場合には、ちょっとしたイレギュラーでパニックになってしまうおそれもあります。そうならないために、ヒアリングシートを用いることもコツのひとつです。ヒアリングシートを作成するお手本が欲しい場合は、インターネットで無料ダウンロードできるサイトが複数あります。
ヒアリングシートは聞き出すべき項目・質問事項を効率的にまとめた資料です。ヒアリングの場に持って行くことで落ち着いて質問できるとともに、うっかり質問漏れを起こしてしまう心配もなくなるでしょう。ヒアリングシートに盛り込む基本的な内容は以下の通りです。
顧客データ・顧客の現状
まずは顧客の基本情報を確認し、顧客の現状把握を行います。聞き出すのは自社が営業をかける種類の商品・サービスについて、現在の利用の有無、有の場合は何を使っているかといった内容です。
顕在化している課題
現状に対して感じている不満や顕在化している課題は、その後の商談につながる重要な情報です。
潜在的な課題の有無
潜在的な課題を発見することで、顧客に現状のデメリットをより強く認識してもらうことができるとともに、自社のソリューション選びにも役立ちます。
課題解決の希望時期
課題によっては急ぐ必要がないケースもありますが、解決の希望時期の把握は重要です。どんなに遅くてもこの時期までに解決したいといった、後ろのスケジュール感を間違えると、解決する意味がなくなってしまったり、納期が間に合わなくなったりといったケースにつながりかねません。
選定基準と利用者
導入する商品・サービスをどのような基準で決定するのか、導入して実際に利用するのは誰かを把握することで、基準にマッチしたソリューション選択や、利用者に訴求するプレゼンテーションに役立ちます。
予算
予算の把握はソリューションの決定に大きく影響します。顧客の希望にマッチするソリューションのプレゼンテーションであれば、円滑な商談の進行を期待できるでしょう。しかし、顧客の予算感を把握しないまま提案を行った場合、コスト感の違いから熱が冷めてしまうかもしれません。
自社のソリューションに対する疑問や印象
自社のソリューションに対する疑問は関心の表れといえるでしょう。しっかりと回答・説明することで理解を得られれば、商談が前に進みます。また、好印象ならより深く理解してらう説明を行えます。逆に印象が悪ければ、改善するためのアプローチを考えたり、他のソリューションを提案したりといった対策が可能です。
導入決定までのプロセス・フロー
課題解決の希望時期はあくまでも後ろの予定ですが、導入決定までのプロセス・フローは商談を進めるうえで気にしておきたい項目です。いまこのプロセスにいるからこのアプローチをといった対応の準備に役立ちます。
決裁権者・キーパーソン
決裁権者とキーパーソンの把握がより重要なことは既述の通りです。相手が決裁権のない人だとは知らずに全力の営業活動を行い良い返事をもらったものの、決裁権者には話が通っていなかった、キーパーソンがメリットを見出さなかったといった理由で失注するという事態を避けるためにも、決裁権者とキーパーソンの確認は欠かせません。
競合状況
競合なくスンナリと契約に至れば良いですが、競合も悪いことばかりではありません。競合相手との状況をヒアリングすることで、見えていなかった課題が浮かんできたり、より顧客にメリットがある優位なソリューションの選択につながったりします。
営業ヒアリングでの注意点

営業のヒアリングにおいて、ヒアリングする内容そのもの以外に注意したい点を2点解説します。
前のめりにならない
売りたい気持ちを抑え、前のめりにならないことが重要です。売上・利益の数字という結果を求める営業のヒアリングである以上、成果に拘るのは必然といえます。しかし、成果に対する思いが前面に出ると、顧客に売り込みに対する警戒心を持たせてしまうことになりかねません。付き合いが浅く関係性が構築できていなければなおさらです。質問・回答の深掘りやプレゼンテーションは相手の様子を見極めて行う必要があります。
直接的な会話に拘らない
ヒアリングといえば会話で行なうものというイメージが強く、実際に会話だけで済むケースは少なくありません。とはいえ、会話に拘り過ぎると行き詰まることもあるでしょう。ヒアリングを円滑に進めるためには、画像・動画や音声など五感を動員した質問や説明が役立ちます。また、事例を提示することで効果的なヒアリングが行えるケースもあるなど、直接的な会話に拘らない考え方が重要です。
ヒアリング力を強化する方法

営業のヒアリング力を強化、スキルのステップアップをする方法は主に3つあります。
ロープレの実施
営業のロールプレイングは営業マン役と顧客役に分かれてヒアリングなど営業活動の実践的な模擬訓練を行う手法で、営業力の向上に広く使われています。本番形式である点と、顧客役や周囲のメンバーから客観的なアドバイスを受けられる点がメリットです。
随行・同行営業
上司や先輩の営業に随行することで、良いお手本に触れて営業力を高めるための参考にすることができます。また、上司や先輩に同行してもらうことで、自分の良い点や悪い点、改善策などのアドバイスをもらえるでしょう。
ITツールの活用
マルチタスクが求められる現代の忙しい営業マンには、ITツールの活用による業務の効率化が求められています。他の業務の効率アップによるヒアリングの準備や実施にかける時間の確保だけでなく、ヒアリング関係の業務自体の効率化が可能です。
これらのヒアリング力の強化方法を実施しているか否かは会社によって異なります。また、実施していたとしても全体か一部かなど程度に差があることも考えられるでしょう。営業での転職を考えているなら、営業に特化した転職支援サービスでヒアリング力を強化しやすい転職先を目指す手もあります。
営業職特化型の転職支援サービスのひとつに9Eキャリアがあります。ぜひ活用をご検討ください。
営業のヒアリングはコツをおさえて効率良く実施しよう
営業のヒアリングは、最終的な成約へ結びつけるために必要な情報を得る重要な業務です。関係性の薄い顧客から貴重な情報を得る作業は簡単ではありません。欠かせない項目を忘れずに、タイミングを外さないヒアリングをするためにはコツの活用がおすすめです。コツをおさえて効率の良いヒアリングを行いましょう。
9Eキャリアで後悔のない営業職転職を
9Eキャリアは、営業職への転職に特化した転職エージェントです。営業未経験者にも対応しており、キャリアの棚卸しから書類添削、面接対策、検索では見つからない非公開求人の紹介まで一貫して無料で支援しています。
また、営業職への転職に特化した”求職者のことを1番に考える”伴走型転職エージェントです。
①“特化型”だからできる、他では出会えない厳選求人
②企業の裏側まで熟知したエージェントによる支援
③書類も面接も通過率が上がる、伴走型の転職支援
という特徴があります。
9Eキャリアの転職支援サービス
具体的にキャリアチェンジ・キャリアアップしたい職種が決まっている方は、下記よりご選択ください。
現時点で職種が決まっていない場合は、転職の目的から最適な職種をご提案します。
この記事の監修者
荒川 翔貴
学生時代に100名規模の営業団体を設立後、大手メーカーで新人賞、売上4,000%増を達成。その後人材業界に転身し、ベンチャー企業にて求職者・企業双方を支援。プレイヤーとして社内売上ギネスを塗り替えながら、3年で事業部長に昇進し組織マネジメントも経験する。
現在は株式会社9Eのキャリアアドバイザーチームリーダーとして、入社半年で再び社内ギネスを更新するなど、常に成果を追求し続けている。(▶︎詳しく見る)
